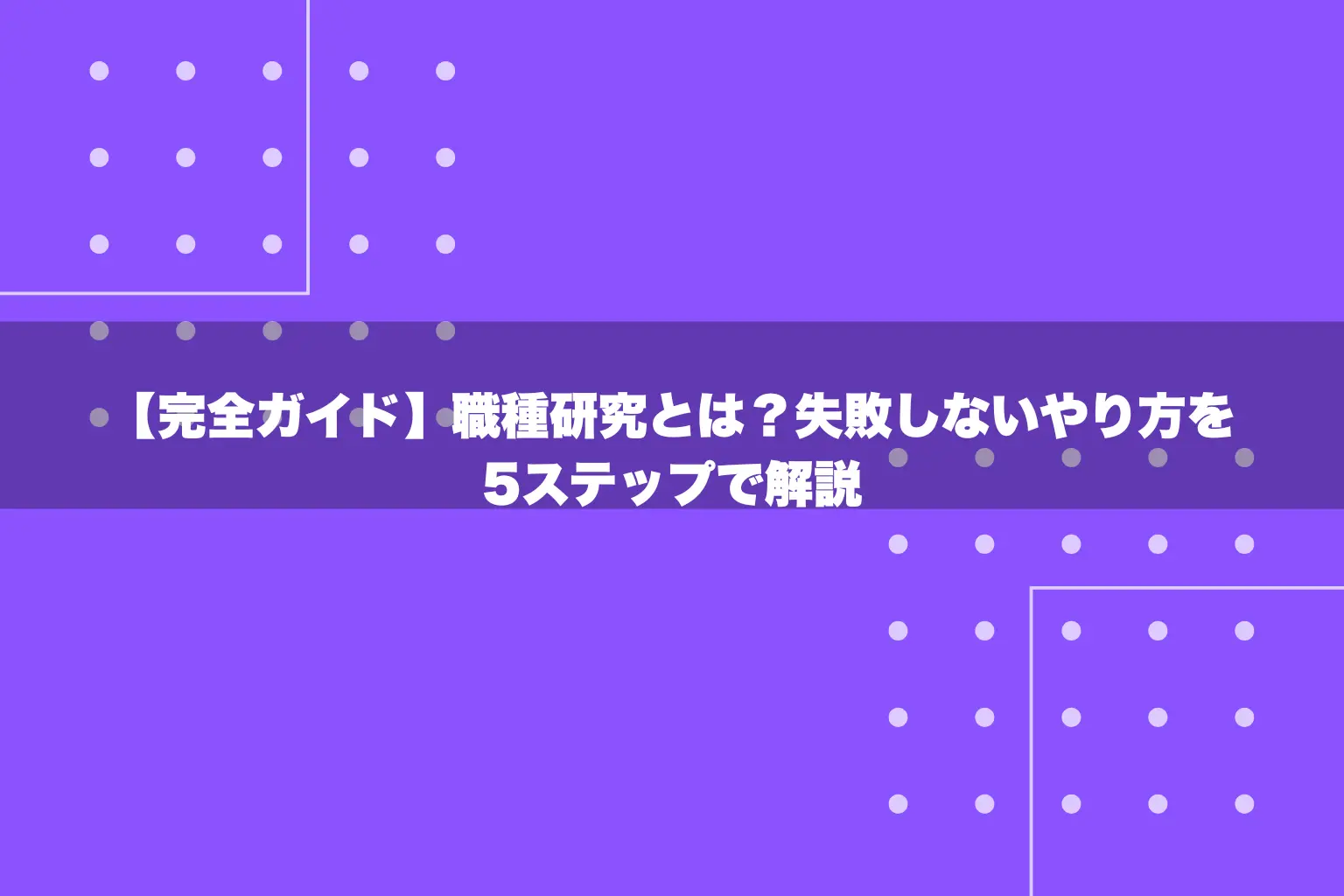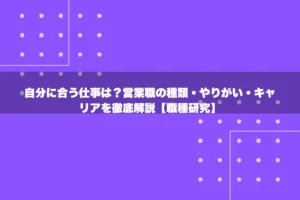職種研究は「自分の軸×仕事のリアル」を重ねる作業。情報を集めるだけでなく、実体験と照らし合わせて理解することで、納得感あるキャリア選択ができる。
対象:自分に合う仕事を客観的に選びたい就活生
メリット:ミスマッチ防止・志望動機に深みが出る・キャリア視野が広がる
注意点:情報収集だけで満足してしまう/人気職種偏重になりやすい
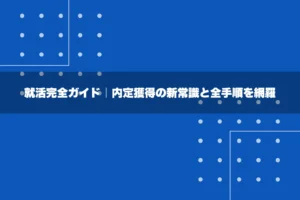
「自己分析はやってみたけど、結局どの仕事が向いているのか分からない…」
「そもそも職種研究って、何から手をつければいいんだろう?」
就職活動を進める中で、多くの大学3年生がこのような悩みを抱えています。周りがインターンや説明会に参加し始めるのを見ると、焦りを感じてしまいますよね。
この記事は、そんなあなたのために書きました。職種研究とは何かという基本から、具体的な進め方、業界研究との違い、そして就活生が陥りがちな失敗例まで、網羅的に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたは「後悔しないキャリア選択のための地図」を手に入れているはずです。漠然とした不安を解消し、自信を持って自分に合う仕事を見つけるための、具体的な第一歩を一緒に踏み出しましょう。
そもそも職種研究とは?就活における重要性を理解しよう
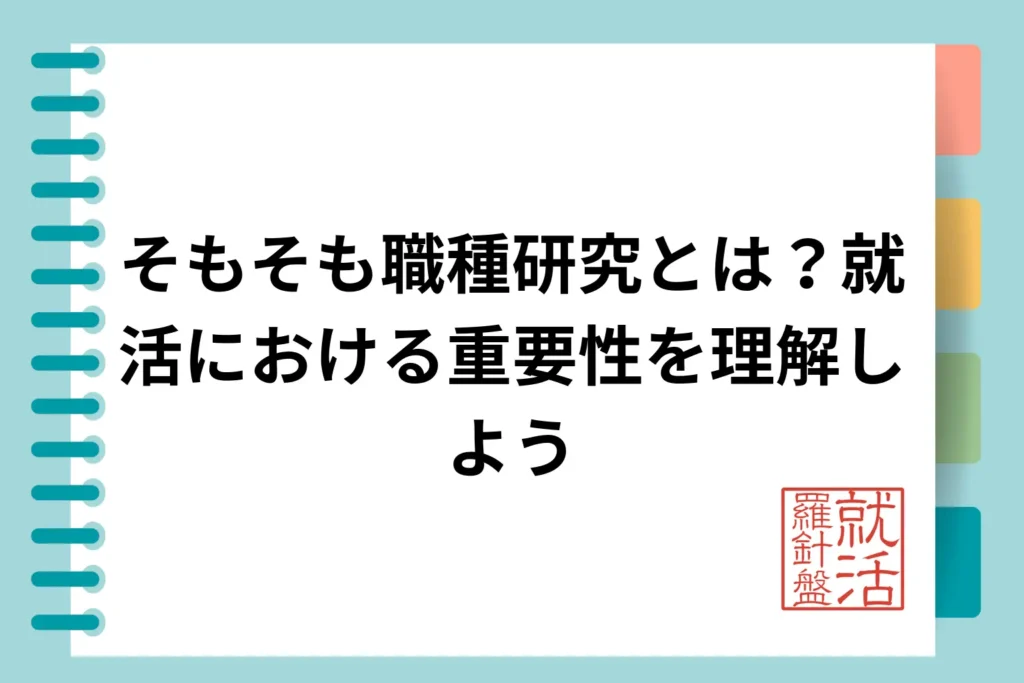
 キャリまる
キャリまる職種研究は「仕事のリアルを可視化し、自分軸と照合するための活動」です。
社会的には、キャリア教育の中心的プロセスとして位置づけられており、単なる情報収集ではなく「意思決定のための比較分析」が目的。
職種理解が浅いと、「思っていた仕事と違う」「成果が出ない」など、離職や燃え尽きに繋がるケースが多い。
職種研究は、厚生労働省「job tag」や日本標準職業分類でも「仕事内容理解を目的とするキャリア形成支援活動」と位置付けられる。
入社後のミスマッチ率(3年以内離職率30%超:厚労省調査)の主因は“仕事内容の誤認”。
職種理解は、ES・面接での説得力向上に直結
まずは基本から押さえましょう。「職種研究」がなぜ就職活動においてこれほど重要なのか、その定義と目的を理解することで、今後の活動がよりスムーズに進みますよ。
職種研究の定義:仕事内容を具体的に知る活動
職種研究とは、一言で言うと「世の中にある様々な仕事(職種)について、その具体的な仕事内容、求められるスキル、やりがい、厳しさなどを詳しく調べる活動」のことです。
「営業職」「事務職」「エンジニア」といった言葉は聞いたことがあっても、実際にどんな一日を過ごし、どのようなミッションを担っているのか、具体的にイメージできる人は少ないのではないでしょうか。
職種研究は、こうした職種ごとの解像度を上げ、自分が働く姿をリアルに想像するための重要なプロセスです。単に名前を知っているだけでなく、その仕事の本質を理解することが、納得のいくキャリア選択に繋がります。
職種研究の3つの目的
なぜ時間をかけて職種研究をする必要があるのでしょうか。その目的は大きく分けて3つあります。これらを意識するだけで、職種研究の質が格段に上がります。
- 入社後のミスマッチを防ぐ
最大の目的は、入社後に「こんなはずじゃなかった…」というミスマッチを防ぐことです。仕事内容を深く理解しないままイメージだけで入社すると、理想と現実のギャップに苦しむことになりかねません。職種研究を通じて仕事のリアルな側面を知ることで、自分に本当に合う環境かを見極めることができます。 - 自分の可能性を広げる
あなたが知っている職種は、世の中に存在する仕事のほんの一部かもしれません。職種研究は、これまで知らなかった魅力的な仕事に出会う絶好の機会です。視野を広げることで、自分の強みや興味を活かせる意外な選択肢が見つかり、キャリアの可能性が大きく広がります。 - 志望動機に深みを持たせる
面接で必ず聞かれる「なぜこの職種を志望するのですか?」という質問。職種研究を徹底していれば、「この職種の〇〇という業務内容が、私の△△という強みを活かせると考えたからです」と、具体的で説得力のある志望動機を語ることができます。これは、他の就活生と差をつける大きな武器になります。
 キャリまる
キャリまるまずは、仕事の本質を“動詞”で捉える練習をしましょう。
例:「営業=売る」ではなく「課題を解決する」「関係を築く」など職種研究を通じて、“何をしたいか”を明確にできれば、企業選び・志望動機作成・キャリア形成すべてがスムーズになります。
業界研究・企業研究との違いと取り組む順番
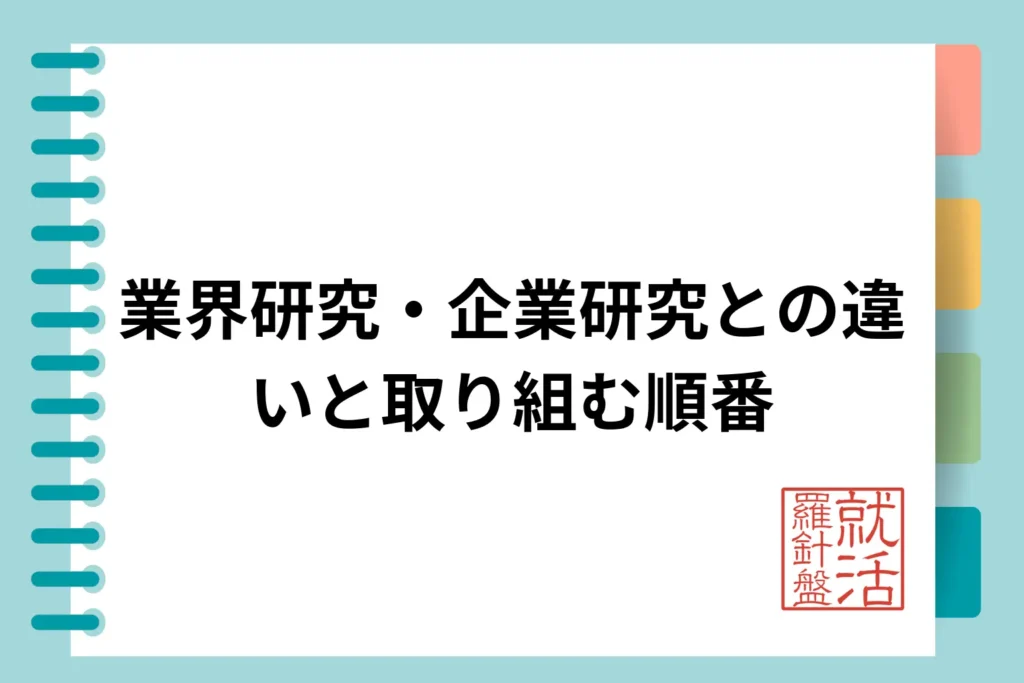
 キャリまる
キャリまる職種研究は、業界研究と企業研究の橋渡しとなるプロセスです。
業界研究で社会全体の仕組みを把握し、職種研究で「自分がどんな立場で貢献したいか」を考えることで、企業研究が具体的に進めやすくなります。
業界=「社会全体の構造」/職種=「個人の役割」/企業=「実践の場」
職種研究を先に行うと、企業選定の軸が明確になりやすい(JREC-IN Career 研究2023)。
採用担当者の8割が「職種理解の深さが志望動機の説得力を高める」と回答(マイナビ2024調査)。
就職活動では、「業界研究」「企業研究」という言葉もよく耳にしますよね。これらと「職種研究」の違いを整理しておきましょう。それぞれの役割と関係性を理解することが、効率的な就活の鍵です。
| 研究の種類 | 対象 | 目的 | 例 |
|---|---|---|---|
| 業界研究 | 産業の分野 | 世の中の仕組みやビジネスの流れを理解する | 自動車業界、IT業界、食品業界など |
| 職種研究 | 仕事の内容 | 具体的な業務内容や働き方を理解する | 営業、人事、システムエンジニアなど |
| 企業研究 | 個別の会社 | その企業ならではの文化や強みを理解する | トヨタ自動車、NTTデータ、味の素など |
これらは独立しているのではなく、密接に関連し合っています。取り組む順番に絶対の正解はありませんが、一般的には「業界研究(社会の全体像を掴む)→ 職種研究(働くイメージを具体化する)→ 企業研究(志望先を絞り込む)」という流れがおすすめです。
ただし、実際にはこれらを行ったり来たりしながら、徐々に志望を固めていくことになるでしょう。
職種研究はいつから始めるべき?
職種研究を始めるのに最適な時期は、大学3年生の夏休みから秋にかけてです。この時期は、サマーインターンシップなどを通じて様々な企業や社会人と接する機会が増え、働くことへの関心が高まるタイミングだからです。
もちろん、もっと早くから始められればそれに越したことはありません。しかし、焦る必要はありませんよ。
大切なのは、自己分析である程度自分のことが見えてきた段階で、業界研究と並行して始めることです。本格的な選考が始まる前に、じっくりと時間をかけて取り組みましょう。
 キャリまる
キャリまる就活の初期段階では、「業界→職種→企業」の順に行うのが基本。ただし、実際には往復しながら進めても構いません。
たとえば「IT業界で働きたい」と思ったら、まず「エンジニア」「営業」「人事」など職種単位で理解を深め、どの役割が自分に合うかを検証しましょう。
【5ステップで解説】失敗しない職種研究の具体的なやり方
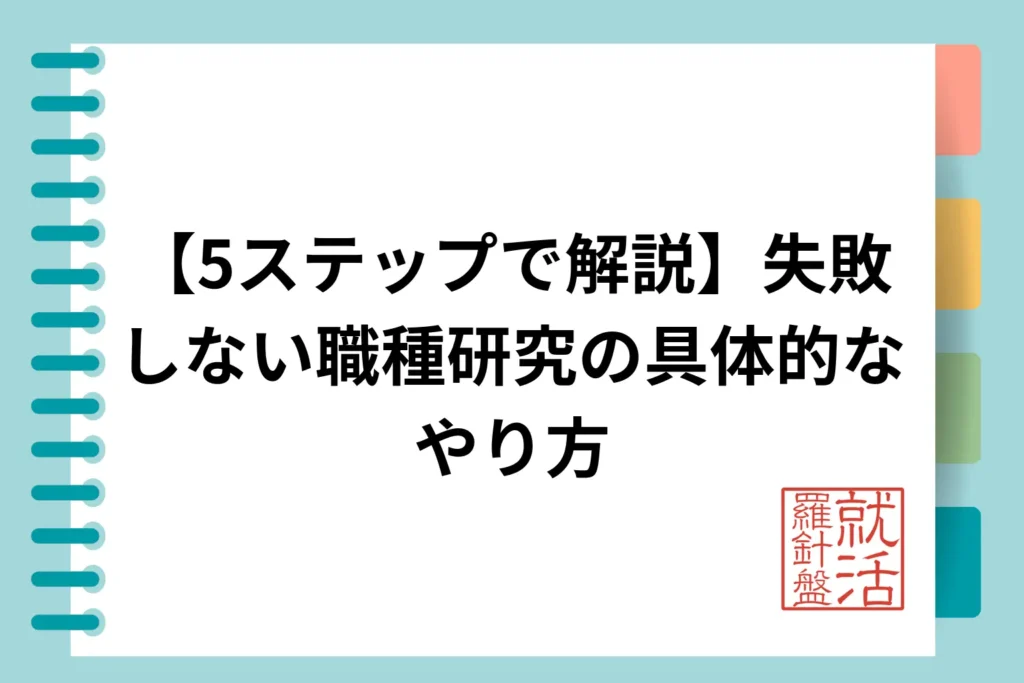
 キャリまる
キャリまる「①自己分析→②職種把握→③興味深掘り→④照合→⑤一次情報収集」という5ステップを踏むことで、就活の軸が明確になります。
特に、ステップ4で「譲れない価値観」を見極め、ステップ5で現場のリアルを確認することで、ミスマッチを防げます。
キャリア理論(ホランド理論・Super理論)でも、「自己理解→職業理解→マッチング→意思決定」が王道プロセス。
早期段階(大学3年夏)から始めた学生は内定満足度が高い。
OB・OG訪問で得た一次情報は志望動機に最も影響。
職種研究の重要性がわかったところで、いよいよ具体的な進め方を見ていきましょう。ここでは、誰でも着実に進められる5つのステップを紹介します。この順番で取り組めば、あなたにぴったりの職種がきっと見つかりますよ。
(※この記事では、自己分析の結果と職種情報を整理できるオリジナルの「職種研究シート」を用意しています。ぜひダウンロードして、シートを片手に読み進めてみてください。あなただけの研究ノートが完成しますよ!)
ステップ1:自己分析で「自分の軸」を明確にする
職種研究の出発点は、「自分を知る」ことです。自己分析で明らかになったあなたの強み、弱み、価値観(何を大切にしたいか)、興味・関心が、職種を選ぶ上での「軸」になります。この軸が曖昧なままだと、たくさんの職種情報に触れても「どれも良さそうに見える…」と迷子になってしまいます。
例えば、「人と協力して目標を達成することに喜びを感じる(強み)」、「安定した環境で着実に成長したい(価値観)」、「IT技術の進化にワクワクする(興味)」といった自己分析の結果を書き出してみましょう。これらが、無数の職種の中から自分に合うものを見つけ出すための羅針盤になります。
ステップ2:世の中にある職種を広く知る
自分の軸が見えたら、次は視野を広げるステップです。まずは先入観を捨てて、世の中にどんな職種があるのかを広く浅く知ることから始めましょう。多くの学生は、テレビCMで見るようなBtoC企業の有名職種(商品企画やマーケティングなど)しか知らない傾向にあります。
しかし、世の中には社会を支える重要なBtoB企業の仕事や、専門的なニッチな職種が無数に存在します。
厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」や、各就活サイトが提供している「職種図鑑」などを活用して、まずはどんな職種のカテゴリがあるのかを眺めてみてください。「こんな仕事もあったのか!」という発見が、あなたの可能性を広げる第一歩です。
ステップ3:興味のある職種を深掘りする
広く職種を眺める中で、少しでも「面白そう」「自分に合っているかも」と感じた職種がいくつか見つかったら、次はそれらを深掘りしていくステップです。ここでは、表面的な情報だけでなく、その仕事のリアルな側面まで徹底的に調べます。
具体的には、以下の項目について情報収集を行い、整理してみましょう。
- 具体的な仕事内容:1日のスケジュール、関わる人、使用するツールなど
- ミッション・役割:その仕事が会社や社会で果たす役割
- やりがい・魅力:どんな時に喜びや達成感を感じるか
- 厳しさ・大変なこと:どんな困難やストレスがあるか
- 求められるスキル・知識:どんな能力や資格が必要か
- キャリアパス:将来どのようなキャリアを歩めるか
これらの情報は、企業の採用サイトや就活サイトだけでなく、現役で働く社会人のインタビュー記事やSNSなども参考にすると、よりリアルな情報を得られますよ。
ステップ4:自分の軸と職種を照らし合わせる
深掘りした職種情報を、ステップ1で明確にした「自分の軸」と照らし合わせる作業です。これが職種研究の最も重要なプロセスと言えるでしょう。
例えば、「人と深く関わり、課題解決を手伝うことにやりがいを感じる」という軸があるなら、営業職の中でも「顧客に寄り添う提案型営業」はマッチ度が高いかもしれません。一方で、「一人で黙々と作業に集中したい」という軸なら、研究開発職やプログラマーなどが候補に挙がるでしょう。
このとき、完璧にすべての軸がマッチする職種を探す必要はありません。「この部分は合っているけど、この部分は少し違うかも」と感じる点を明確にすることが大切です。その上で、自分の中で何が譲れない価値観なのかを考え、優先順位をつけていきましょう。
ステップ5:OB・OG訪問やインターンシップでリアルな情報を得る
Webサイトや本で得られる情報は、いわば二次情報です。職種研究の仕上げとして、必ず一次情報、つまり「生の声」に触れる機会を持ちましょう。その最も効果的な方法が、OB・OG訪問やインターンシップです。
実際にその職種で働く先輩に、「仕事で一番大変なことは何ですか?」「どんな時にやりがいを感じますか?」といった具体的な質問をぶつけてみましょう。Web上では得られない本音や、現場のリアルな雰囲気を感じ取れるはずです。
インターンシップに参加すれば、実際に業務を体験できるため、その職種が自分に合うかどうかを肌で感じることができます。この「生の情報」こそが、あなたの最終的な意思決定を後押ししてくれるでしょう。
 キャリまる
キャリまる職種研究は“ノートにまとめる”ことで理解が定着します。
おすすめは「職種研究シート」:
職種名/仕事内容
求められるスキル
やりがい/厳しさ
自分の強みとのマッチ度(5段階評価)
ExcelやNotionで管理すれば、OB訪問のメモや気づきを蓄積できます。
どんな仕事がある?【分野別】職種一覧と情報収集の方法
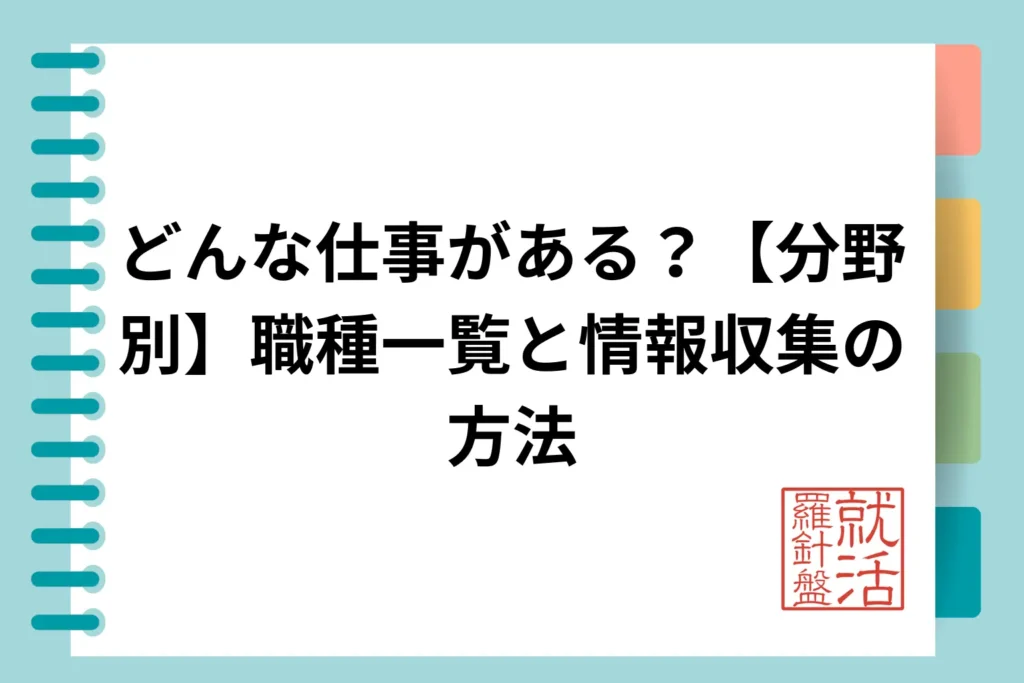
 キャリまる
キャリまる職種は大きく「事務・管理系」「営業・販売系」「企画・マーケティング系」「技術・IT系」「クリエイティブ系」「専門職系」に分類されます。
重要なのは、“名前で選ばず、役割と成果物で理解する”こと。
たとえば営業職でも、法人営業と個人営業では必要スキルも目標も異なります。
自分の得意分野が「人・モノ・情報・数字」のどれに近いかで、最適な職種群を見極めることが可能です。
日本の職種体系は、総務省の「日本標準職業分類」と厚生労働省の「job tag」に基づき約700種以上に整理されており、分類理解がキャリア選択の精度を高める。
実際の就職市場では、「文系=営業・企画系」「理系=技術・研究系」に偏りがちだが、職種横断スキル(データ分析・顧客提案・人材開発)を軸にすれば柔軟なキャリア形成が可能
情報収集では「一次情報(社員インタビュー・職場体験)」と「二次情報(統計・職業データ)」を組み合わせることが有効。特にjob tagは業務内容・必要スキル・関連資格を体系的に閲覧可能。
「世の中にどんな職種があるか広く知ろうと言われても、何から見ればいいかわからない…」という方のために、ここでは代表的な職種の分類をいくつか紹介します。これらの分類はあくまで一例です。まずは大枠を掴んで、興味のある分野から深掘りしてみてくださいね。
(※本記事で紹介する職種は、総務省の「日本標準職業分類」や厚生労働省の「job tag」などを参考に分類しています。)
事務・管理系職種
企業の活動を円滑に進めるために、組織全体を支える重要な役割を担う職種群です。コミュニケーション能力や正確な事務処理能力が求められます。
- 一般事務・営業事務:書類作成や電話応対、データ入力など、部署のサポート業務全般を行います。
- 人事:採用、研修、労務管理、制度設計など、「人」に関わる業務を担当します。
- 経理・財務:会社のお金の流れを管理します。決算業務や資金調達などが主な仕事です。
- 総務:備品管理やオフィス環境の整備、株主総会の運営など、会社全体の庶務を担当します。
 現役人事の声
現役人事の声人事の仕事は華やかに見られがちですが、地道な調整業務や制度の知識が不可欠。でも、自分が採用した人が活躍する姿を見るのが何よりのやりがいです。
営業・販売系職種
自社の製品やサービスを顧客に提案し、契約に結びつけることで、会社の売上を直接生み出す職種です。課題発見力や関係構築力が重要になります。
- 法人営業(BtoB):企業を顧客として、製品やサービスを提案します。
- 個人営業(BtoC):一般消費者を顧客として、不動産や自動車、保険などを販売します。
- 販売・接客:店舗でお客様と直接関わり、商品の説明や販売を行います。
- 海外営業:海外の企業を相手に、製品やサービスの販売、交渉を行います。
企画・マーケティング系職種
市場のニーズを分析し、新しい商品やサービスを考え出したり、その魅力を世の中に広めたりする仕事です。情報収集力や発想力が求められます。
- 商品企画:市場調査から新商品のコンセプト立案、開発までを担当します。
- マーケティング:広告宣伝や販売促進活動を通じて、商品が売れる仕組みを作ります。
- 広報・PR:メディア対応やプレスリリース配信などを通じて、企業の認知度やイメージ向上を図ります。
- Webディレクター:Webサイトの企画・制作・運営の責任者として、プロジェクト全体を管理します。
IT・技術系職種
専門的な知識やスキルを活かして、新しい技術を生み出したり、ITシステムを構築したりする仕事です。論理的思考力や探究心が重要になります。
- システムエンジニア(SE):顧客の要望をヒアリングし、システムの設計・開発を行います。
- プログラマー:SEが作成した設計書をもとに、プログラミング言語を用いてシステムを構築します。
- Webデザイナー:Webサイトのデザインやコーディングを担当します。
- 研究開発:新しい技術や製品を生み出すための基礎研究や応用研究を行います。
おすすめの情報収集サイト・ツール
職種を広く知る、あるいは深掘りするために役立つサイトやツールを紹介します。これらをブックマークしておくと、効率的に情報収集ができますよ。
| ツール名 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| job tag(厚生労働省) | 全国のハローワークの求人情報などに基づいた公的データが豊富。仕事内容の動画も見られる。 | 信頼性の高い情報で、職種を網羅的に知りたい人 |
| 就職四季報 | 企業の採用データが詳細に掲載。職種別の採用人数などもわかることがある。 | 志望企業群が決まってきて、より具体的な情報を知りたい人 |
| 各就活情報サイト | ONE CAREER、リクナビ、マイナビなど。職種図鑑や先輩の体験談が豊富。 | まずは広く浅く、様々な職種の概要を知りたい人 |
| 企業の採用サイト | 「社員紹介」や「仕事内容」のページは情報の宝庫。リアルな働き方がわかる。 | 興味のある企業が見つかり、その中での働き方を知りたい人 |
 キャリまる
キャリまる情報収集では、まず「公的データ+就活サイト+現場の声」の3軸を組み合わせましょう。
job tag(厚労省):職種解説・動画・関連資格
ONE CAREER/リクナビ職種図鑑:内定者体験談
企業採用サイト:実務スケジュール・社員紹介
さらに、LinkedInで職種名を検索すると、現職者のキャリアパスやスキルタグが見られます。
これらをまとめてExcelで可視化することで、自分に合う職種が明確になります。
職種研究シート(保存機能付き)
気になる職種を入力して比較してみましょう。
入力内容は自動で保存されます(ブラウザを閉じても保持)。
就活生が陥りがちな職種研究の失敗例と対策
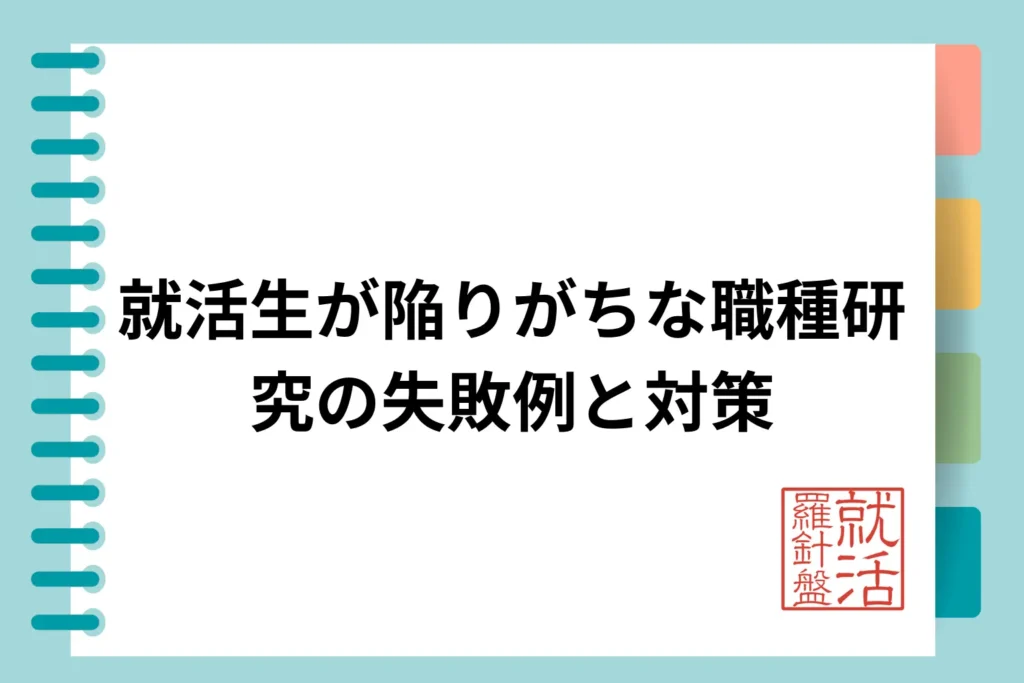
 キャリまる
キャリまる最大の失敗は、イメージで判断すること。
営業=体育会系、企画=華やか、エンジニア=理系専用…などの思い込みは危険です。
本質を理解せずに志望すれば、入社後ギャップに直面します。
「人気職種偏重」により選択肢を狭める傾向
職種イメージの誤解が離職の原因に
ミスマッチ防止には、実地体験とフィードバックが最も効果的
職種研究を一生懸命やっているつもりでも、実は落とし穴にはまってしまうことがあります。ここでは、多くの就活生がやりがちな失敗例とその対策を紹介します。これを読んで、同じ轍を踏まないようにしましょう。
失敗例1:イメージだけで判断してしまう
「営業は体育会系で大変そう」「企画職はキラキラしていて楽しそう」といった、漠然としたイメージだけで職種を判断してしまうのは非常に危険です。実際には、顧客とじっくり向き合うコンサルティング営業もあれば、データ分析や地道な調整業務が多い企画職もあります。
対策としては、ステップ5で紹介したように、必ず一次情報に触れることです。OB・OG訪問やインターンシップを通じて、その仕事のリアルなやりがいや厳しさを自分の目で確かめましょう。「イメージと違った」という発見こそが、職種研究の大きな成果です。
失敗例2:有名・人気職種にしか目を向けない
多くの学生が知っている総合商社や大手メーカー、広告代理店などの人気職種は、当然ながら倍率も非常に高くなります。これらの職種だけに視野を狭めてしまうと、自分に合う他の素晴らしい仕事を見逃してしまうかもしれません。
特に、一般消費者には馴染みが薄いBtoB(企業向けビジネス)企業には、高い技術力を持つ優良企業がたくさん隠れています。
対策は、ステップ2「世の中にある職種を広く知る」を意識的に行うことです。自分の知らない業界や企業にも積極的に目を向け、合同説明会などで話を聞いてみると思わぬ出会いがあるかもしれません。食わず嫌いをせず、視野を広く持つことが、後悔しない選択に繋がります。
 キャリまる
キャリまる職種選びの基準は「やりたい」よりも「続けられるか」。
1日や週単位の仕事内容を具体的に想像し、どの作業に充実感を覚えるかを分析しましょう。
また、OB訪問では“成功談”より“失敗談”を聞くのが効果的。リアルな難しさを知ることが、納得のキャリア選択に繋がります。
職種研究Q&A
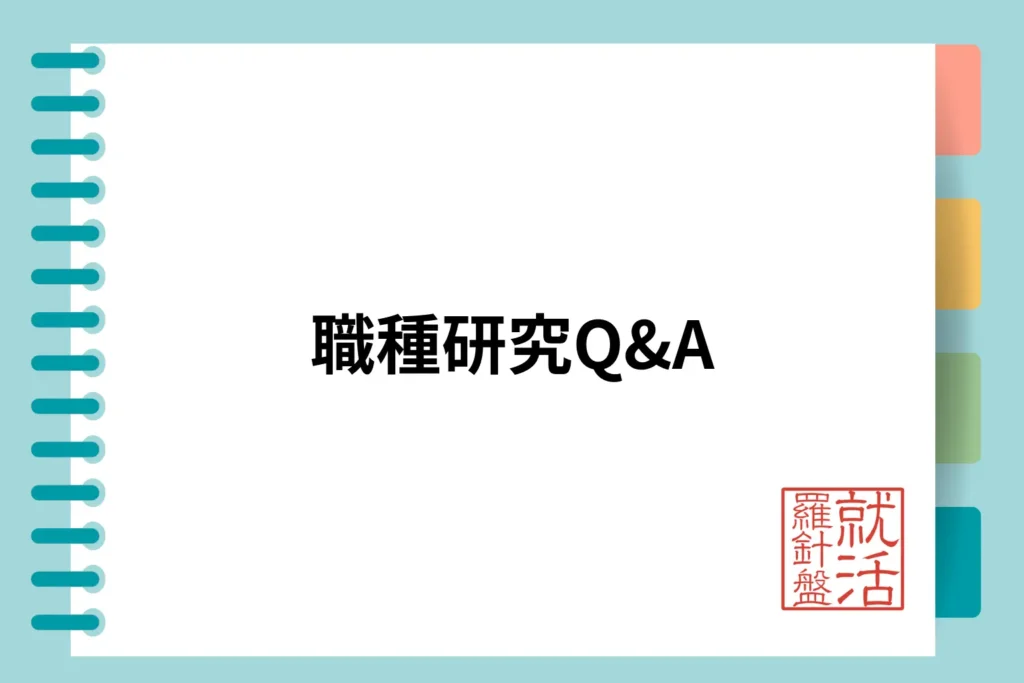
職種研究と業界研究のどちらを先にすべき?
まずは業界研究から始めるのが基本です。業界を広く理解してから職種を選ぶ方が、ミスマッチを防ぎやすく、企業選びの軸を作りやすいです。
エビデンス
- 厚生労働省「新卒応援ハローワーク」では、業界全体の構造と動向を理解した上で職種選択を行うことが望ましいと明記。
- 経団連「採用選考に関する指針」でも、学生は「業界理解→職種理解→企業理解」の順で行動するのが効果的と推奨。
- JASSO「キャリア支援ハンドブック」では、業界を俯瞰してから職種を絞る方が将来のキャリア選択の幅を保てると説明。
対応策
業界研究(全体把握)
んな業界があるか、将来性・市場規模・安定性を比較。経済産業省の「業種別動向データ」や日経業界地図が有効。
職種研究(具体的な働き方の理解)
各業界の中で「営業・企画・エンジニア・事務」などの仕事内容・スキルを整理。同じ職種でも業界によって業務内容が大きく異なる点に注意。
業界×職種の掛け合わせで志望軸を設定
「金融業界 × コンサルティング職」「メーカー × 技術開発職」など。この段階でOB訪問を行うと、現場のリアルを知れる。
 キャリまる
キャリまる就活初期は 業界研究 → 職種研究 → 企業研究 の順がベスト。
業界を先に理解することで、自分の強みをどの職種で活かせるかが明確になり、志望動機の説得力も高まります。
職種研究を深めるには?
実際に働く人の話を聞くことが最も効果的です。求人票や採用ページで業務内容を把握し、OB訪問やインターンで現場のリアルを体験することで理解が深まります。
エビデンス
- 厚生労働省「新卒応援ハローワーク」では、職種理解には“現場の声”を聞くことが重要と明記。
- 経団連「採用選考に関する指針」でも、学生は職種研究を通じて自身の適性と企業の求める能力を照合する必要があると示す。
- JASSO「キャリア支援ハンドブック」では、体験型学習(インターン・職場訪問)が最も効果的な職種理解方法と紹介。
対応策
基礎情報を集める
求人票・企業採用サイト・厚労省「職業情報提供サイト(jobtag)」で仕事内容・スキル・年収帯を確認。同じ「営業職」でも、業界により提案内容・評価基準が異なる。
実務者の話を聞く(OB・OG訪問)
具体的な1日の流れ・やりがい・大変な点を質問。「なぜその職種を選んだか」「他職種との違い」を聞くと視野が広がる。
体験してみる(インターン参加)
短期・長期どちらでも可。実際の業務を通じて自分の適性を確認。インターン体験はES・面接の具体的エピソードにも活用できる。
 キャリまる
キャリまる職種研究を深めるには、①調べる → ②聞く → ③体験する の3ステップが最も効果的。
机上の理解ではなく、“人と現場に触れる”ことで自分の適性と理想の働き方が見えてきます。
職種研究はいつから始めるべき?
大学3年の春(3〜5月)から始めるのが理想です。夏のインターン前に職種を理解しておくと、ESや面接で志望動機が明確になり、内定率が高まります。
エビデンス
- 厚生労働省「新卒応援ハローワーク」では、3年春〜夏を“自己理解・職業理解の開始時期”と定義。
- 文部科学省「キャリア教育推進ガイドライン」でも、大学3年次に職業理解を深める活動を重点化と記載。
- リクルート「就職白書2024」によると、内定者の約45%が3年春〜夏に職種を確定していた。
- 経団連「採用活動スケジュール」では、3年夏のインターンが本選考直結型であるため、事前準備が重要と明示。
対応策
3年春:基礎調査を開始
厚労省「職業情報提供サイト(jobtag)」で職種一覧を確認。業務内容・必要スキル・年収帯を比較すると理解が深まります。
3年夏:インターン前に理解を整理
志望職種ごとの仕事の流れを把握し、質問を用意。現場社員に話を聞くことで「自分に合うか」を判断しやすくなります。
3年秋以降:志望職種を確定・深化
インターン経験を踏まえ、本選考に向けて志望動機を具体化。この段階でOB訪問や企業比較を行うと、職種理解が面接力につながります。
 キャリまる
キャリまる職種研究の開始時期は 大学3年春(3〜5月) が最適。
インターン前に理解を深めることで、自分の適性が明確になり、選考対策の精度も上がります。
職種研究と業界研究の違いは?
業界研究は“どんな分野の企業があるか”を知ることで、職種研究は“その中で自分がどんな仕事をするか”を知ることです。つまり、業界が「舞台」、職種が「役割」です。
エビデンス
- 厚生労働省「新卒応援ハローワーク」では、業界研究=企業群の特徴理解、職種研究=仕事内容・適性の理解と明示。
- 文部科学省「キャリア教育推進ガイドライン」も、業界理解(産業構造)と職業理解(職務内容)は別段階で学ぶべきと定義。
- JASSO「キャリア支援ハンドブック」では、業界研究が“興味の方向性づくり”、職種研究が“自分の活躍領域の発見”と整理。
対応策
業界研究:市場全体の構造を理解する
各業界の特徴、将来性、主要企業を比較。経済産業省の「業種別動向データ」や日経業界地図が有効。
職種研究:自分がどう働くかを具体化する
営業・企画・開発・管理などの仕事内容と求められるスキルを整理。厚労省「職業情報提供サイト(jobtag)」で職種別スキルや平均年収を確認可能。
業界×職種を組み合わせて志望軸を作る
例:「メーカー業界×技術職」「IT業界×営業職」など。この“掛け合わせ”が明確だと、ES・面接で説得力が増します。
 キャリまる
キャリまる業界研究=「どの分野で働くか」
職種研究=「その分野で何をするか」
両方を組み合わせてこそ、自分に合った仕事選びと説得力のある志望動機が完成します。
職種研究の目的は?
自分の強みや興味を活かせる仕事を見つけるためです。仕事内容・必要スキル・やりがいを理解することで、入社後のミスマッチを防ぎ、志望動機の説得力が高まります。
エビデンス
- 厚生労働省「新卒応援ハローワーク」では、職種理解は“自己理解と職業選択の橋渡し”と明記。
- 文部科学省「キャリア教育推進ガイドライン」も、職種研究の目的は“適性と希望をすり合わせること”と定義。
- JASSO「キャリア支援ハンドブック」では、職種研究を行う学生の方が入社後の定着率が高いと報告。
- リクルート「就職白書2024」によると、内定者の約7割が職種理解を深めてからエントリーしていた。
対応策
仕事内容を具体的に理解する
厚労省「職業情報提供サイト(jobtag)」で職務内容・スキル・年収を確認。同じ職種名でも業界によって仕事内容が異なる点に注意。
自分の適性と照らし合わせる
得意分野・性格特性(MBTIや自己分析結果)と職種の特徴を比較。「人と話すのが得意→営業職」「分析が得意→企画職」など軸を明確に。
志望動機や将来像に落とし込む
その職種で何を実現したいかを言語化。面接での「なぜこの職種か?」に一貫して答えられるようにする。
 キャリまる
キャリまる職種研究の目的は、自分の適性と仕事内容の接点を見つけること。
“何をする仕事か”を理解すれば、志望動機が具体化し、入社後の後悔を防ぐことにつながります。
職種を絞りすぎるのは良くない?
はい、就活初期に職種を1つに絞りすぎるのはリスクがあります。選択肢が狭まり、チャンスを逃す可能性があるため、2〜3職種を比較しながら進めるのが理想です。
エビデンス
- 厚生労働省「新卒応援ハローワーク」は、職種や業界を早期に限定しすぎるとミスマッチが起こりやすいと注意喚起。
- 文部科学省「キャリア教育推進ガイドライン」でも、初期段階では“探索的キャリア形成”を推奨。幅広い職業理解を通じて適性を見つけるべきと明記。
- リクルート「就職白書2024」では、内定獲得者の65%が2職種以上を比較検討していたというデータあり。
- 経団連「採用選考指針」も、学生に対して「多角的な業界・職種の理解」を求めている。
対応策
初期段階:2〜3職種を候補に設定
営業・企画・技術などジャンルの異なる職種を比較。それぞれの“求められる力”を調べると、自分の強みが見えやすい。
中期段階:体験を通して絞り込み
インターンやOB訪問で実際の仕事内容を確認。想像と現実のギャップを埋めることが大切。
終盤:志望職種を1つに決定
面接対策やESで一貫したストーリーを作る段階で明確化。「最終的にどの職種で成長したいか」を言語化する。
 キャリまる
キャリまる職種を最初から1つに絞りすぎるのはNG。
就活序盤は「広く知って、後で選ぶ」姿勢が大切です。
比較する過程で、自分に本当に合う仕事・働き方が見えてきます。
職種を変えたいと思ったら?
まずは現在の職種で得たスキルを棚卸しし、共通点のある職種を目指すのがおすすめです。転職だけでなく、社内異動やスキル習得によるステップチェンジも有効です。
エビデンス
- 厚生労働省「キャリア形成支援制度」では、職種変更は“キャリアの自然な発展段階”と定義。
- 文部科学省「キャリア教育推進ガイドライン」でも、“キャリアの柔軟性”が職業満足度に直結すると明記。
- 経済産業省「リスキリング支援ガイド」では、スキルの再学習により職種転換の成功率が向上すると報告。
- リクルート「転職白書2024」によると、転職者の約3割が“未経験職種への挑戦”で成功している。
対応策
スキル棚卸しと自己分析
現職で得たスキル・実績・得意分野を洗い出す。厚労省「jobtag」やリクルート「職種チェンジ診断」を活用すると整理しやすい。
共通スキルを活かせる職種を探す
営業→企画/接客→人事/エンジニア→PMなど。完全未経験より“スキル連続性”のある職種が成功しやすい。
学び直し・社内異動・転職を検討
社内の異動制度を利用、または外部スクールや資格でリスキリング。職種変更希望は早めに上司・人事に相談するのが◎。
 キャリまる
キャリまる職種を変えたいと思ったら、「スキルの共通点を見つけて橋渡しする」ことがカギ。
転職だけでなく、学び直しや社内異動という“ゆるやかな職種転換”も立派なキャリア戦略です。
職種研究を深めるおすすめサイトは?
厚生労働省の「職業情報提供サイト(jobtag)」がおすすめです。公的データで職種ごとの仕事内容・スキル・年収が確認でき、業界や興味分野別にも検索できます。
エビデンス
- 厚生労働省「職業情報提供サイト(jobtag)」は、日本版O-NET(職業データベース)として公的に運営されており、職種ごとのスキル・適性・労働条件を客観的に閲覧可能。
- 文部科学省「キャリア教育推進ガイドライン」でも、職業理解には公的情報源の活用が望ましいと記載。
- 経済産業省「業種別動向データ」やリクルート「就職みらい研究所」も、職種別トレンド・将来性分析に活用できる。
対応策
厚生労働省「jobtag」で職種の全体像を把握
https://shigoto.mhlw.go.jp の職種検索から仕事内容・スキル・必要資格・平均年収を確認。「職業興味検査(VPI)」を受けると、自分に合う職種を自動提案してくれます。
経済産業省データで業界トレンドを確認
各業界での主要職種・需要変化・スキル動向を把握。
 キャリまる
キャリまる職種研究を深めるなら、「jobtag」で基礎理解+民間サイトで現場感を補う二段構えが最強。
信頼性とリアルを組み合わせることで、自分に合った職種のイメージが具体化します。
出典URL
- 厚生労働省:職業情報提供サイト(jobtag)
- https://shigoto.mhlw.go.jp
- 文部科学省:キャリア教育推進ガイドライン
- https://www.mext.go.jp
- 経済産業省:業種別動向データ
- https://www.meti.go.jp
- リクルート:就職みらい研究所
- https://www.recruit.co.jp
まとめ:職種研究は後悔しないキャリア選択の第一歩
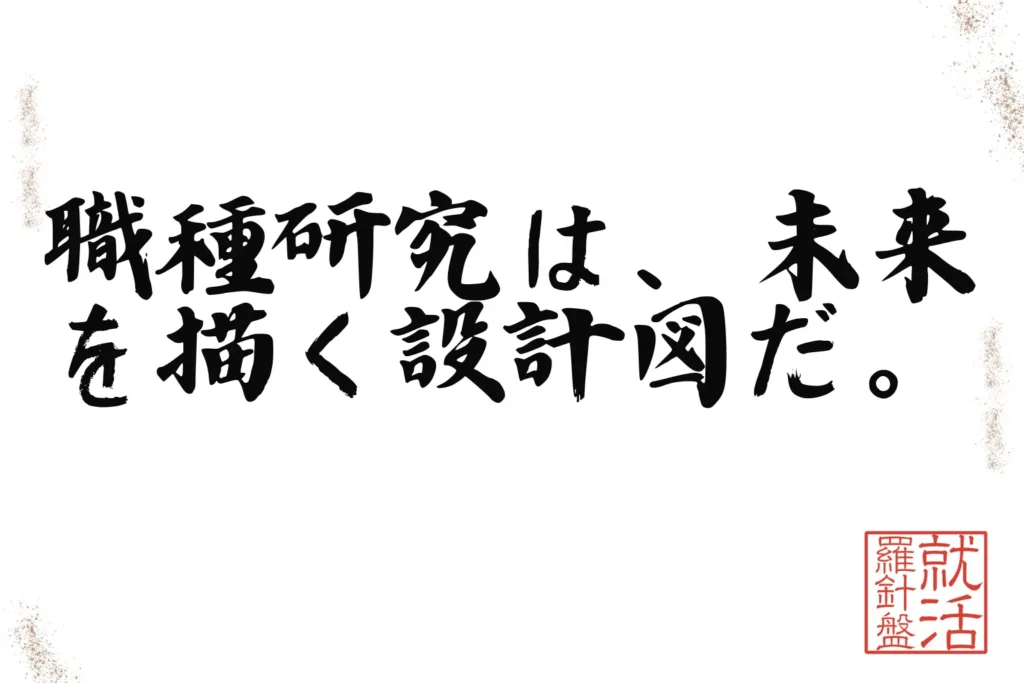
今回は、職種研究の目的から具体的な5つのステップ、そして失敗しないための注意点までを詳しく解説してきました。
職種研究は、単に就活の選考を突破するためだけのものではありません。あなた自身の価値観と社会を結びつけ、心から納得できるキャリアを歩むための羅針盤となる、非常に重要な活動です。時間と手間はかかりますが、ここでじっくり自分と仕事に向き合った経験は、あなたの社会人人生の大きな財産になるはずです。
この記事を読んで、「何から始めればいいか」が見えてきたのではないでしょうか。まずはステップ1の自己分析の結果をもう一度見直すことから始めてみましょう。そして、紹介したサイトなどを活用して、一つでも多くの職種に触れてみてください。あなたの輝ける場所が、きっと見つかります。応援しています!
参考サイト
- 厚生労働省「job tag」・「職業分類2024」
- 経団連「採用と大学教育改革に関するアンケート」
- リクルートキャリア「就職プロセス調査2024」
- パーソル総合研究所「就業意識白書2024」
- 文部科学省「キャリア教育推進指針2025」