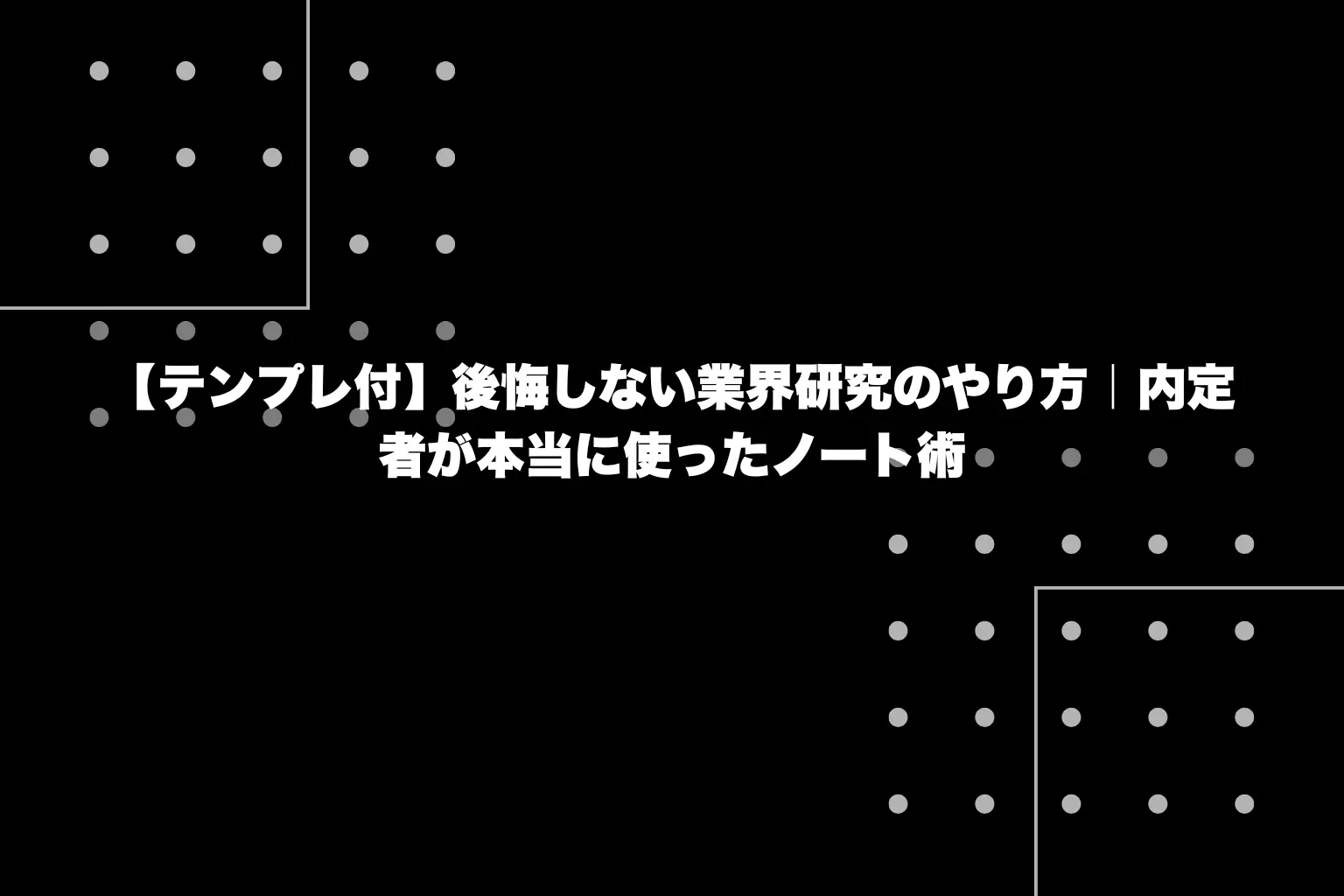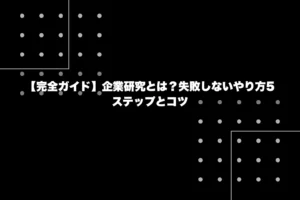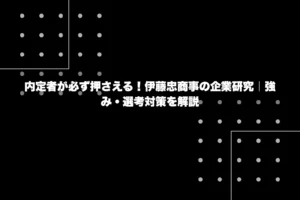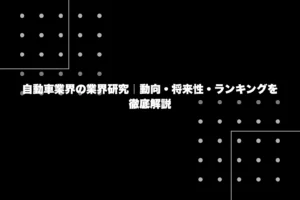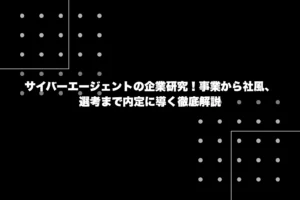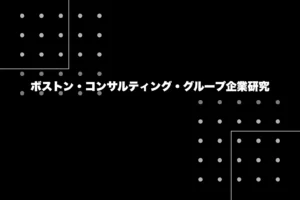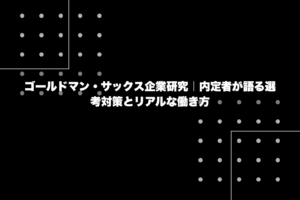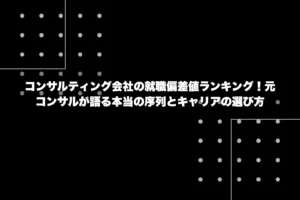業界研究は「情報収集」ではなく「自己理解と志望動機形成」のプロセス。5ステップで体系的に進め、ノートに自分の考えを言語化することで、後悔しない企業選びができる。
対象:何から始めるか迷う就活初期の学生、自己分析を終えた人
就活の初期段階で「何から始めるべきか」迷っている学生。自己分析と業界理解を結びつけたい人に最適。
メリット:志望動機が具体化し、面接で説得力が増す
自分軸で業界を選定でき、志望動機の深掘りが可能に。面接やESでも説得力のある発言ができるようになる。
注意点:情報をまとめるだけで満足する「まとめ病」になりやすい
情報を詰め込みすぎて「まとめただけ」で終わる危険性。目的を失うと時間ばかりかかり、非効率になる。
\ どの業界が向いているかスグにわかる! /
「周りが就活を始めて焦るけど、業界研究って何から手をつければいいの…?」
「そもそも、何のためにやるのか目的もわからない」
就職活動の第一歩として誰もが耳にする「業界研究」。しかし、その重要性は分かっていても、具体的な進め方や目的が分からず、途方に暮れてしまう学生は少なくありません。
この記事では、そんなあなたのための「業界研究の完全攻略ガイド」です。業界研究の目的といった基本的な内容から、内定者が実践した具体的な5つのステップ、情報収集のコツ、そして面接で「おっ」と思わせるアウトプットに繋がる「業界研究ノート」の作り方まで、余すところなく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたは以下の状態になっています。
- 業界研究の目的と全体像を理解し、「まず何をすべきか」が明確になっている
- 提供されるテンプレートを使い、すぐに行動を開始できる
- 自分に合った業界を見つけるための「自分だけの軸」の重要性に気づく
- 「後悔しない企業選び」に向けて、自信を持って就活を進められる
業界研究とは、未来の自分を幸せにするための「解像度」を上げる作業です。なんとなくで企業を選ぶのではなく、納得感を持ってキャリアの第一歩を踏み出しましょう。
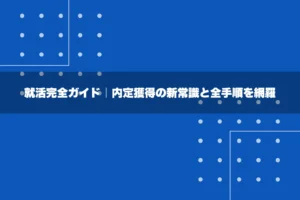
そもそも業界研究とは?目的を理解すればやる気が出る!
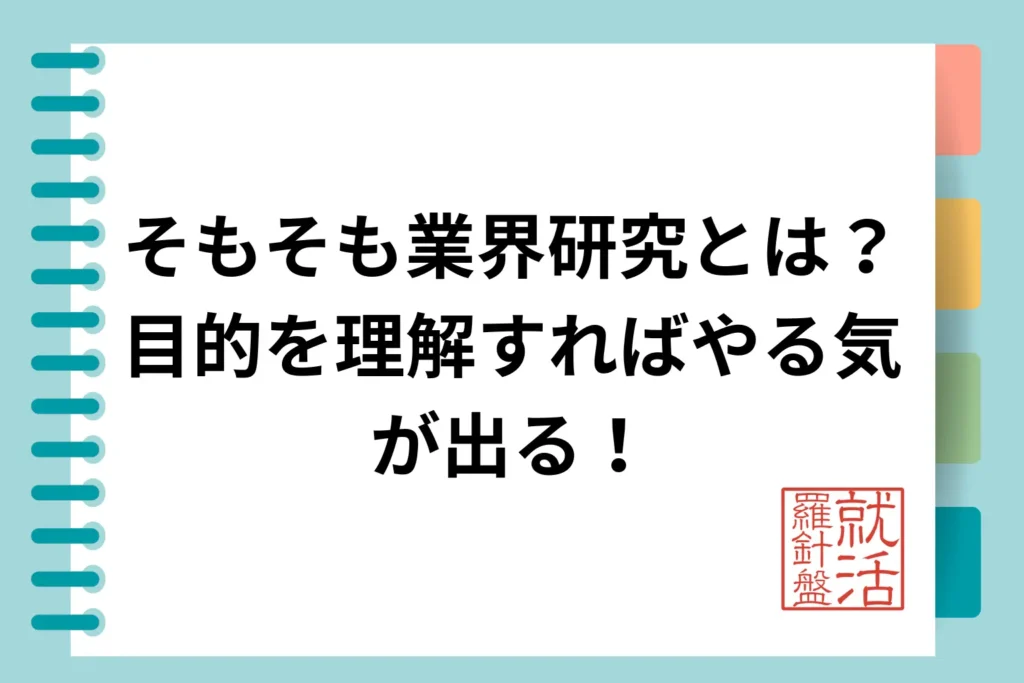
 キャリまる
キャリまる業界研究は単なる知識習得ではなく、「自分がどこで価値を発揮できるか」を明確にする分析作業です。企業理解の前に業界構造を俯瞰することで、自分に合う職種・働き方・将来像が見えてきます。
業界研究はミスマッチ防止・志望動機形成・選択肢拡大が目的。
就職四季報・業界地図・IRが一次情報源。
BtoB企業の理解が「隠れ優良企業」発見につながる。
「とりあえず始めなきゃ」と手を動かす前に、まずは「なぜ業界研究をするのか」という目的をしっかり理解しましょう。目的が分かれば、やるべきことが明確になり、モチベーションも格段に上がります。業界研究には、大きく分けて3つの重要な目的があります。
目的①:入社後のミスマッチを防ぐ
業界研究の最大の目的は、入社後の「こんなはずじゃなかった…」というミスマッチを防ぐことです。世の中には、華やかに見える業界の裏に隠れた厳しい現実や、地味に見えて実は非常に安定していて働きやすい業界など、様々な側面があります。
例えば、「面白そう」という理由だけで広告業界を志望しても、業界特有の長時間労働や厳しい競争環境を知らずに入社すれば、理想と現実のギャップに苦しむかもしれません。業界のビジネスモデル、将来性、働き方、文化などを深く理解することで、自分の価値観や適性に本当に合った場所なのかを判断でき、後悔のない選択に繋がります。
目的②:志望動機に深みと説得力を持たせる
面接で必ず聞かれる「志望動機」。ここでライバルと差をつける鍵も、業界研究にあります。「なぜ他の業界ではなく、この業界なのですか?」という質問に対し、業界の現状や将来性、社会における役割などを踏まえた上で、「だからこそ、私はこの業界でこんなことを成し遂げたい」と語れれば、その志望動機には圧倒的な説得力が生まれます。
業界の課題を正確に捉え、それに対して自分ならどう貢献できるかを具体的に述べることができれば、人事担当者に「この学生はよく調べているな」「本気度が高い」という印象を与え、高く評価されるでしょう。
目的③:知らなかった優良企業に出会うチャンスを広げる
あなたの知っている企業は、世の中に存在する企業のほんの一部に過ぎません。特に、一般消費者向けの製品やサービスを扱わないBtoB(Business to Business)企業の中には、世界トップシェアを誇る隠れた優良企業がたくさん存在します。
業界研究を通して視野を広げることで、これまで名前も知らなかったけれど、実は自分の興味や強みにぴったり合う魅力的な企業に出会える可能性が飛躍的に高まります。
知名度やイメージだけで選択肢を狭めるのではなく、業界全体の構造を理解することで、本当に自分にとっての「良い会社」を見つけ出すことができるのです。
参考
- 経済産業省「産業構造ビジョン2024」
- 東洋経済『業界地図2025』
 キャリまる
キャリまるまず『業界地図(日経BP)』や『就職四季報(東洋経済)』を1冊読み、業界の構造を俯瞰しましょう。就活初期は幅広く興味を持ち、狭く深くに進めるのがコツです。
【5ステップで完成】後悔しない業界研究のやり方
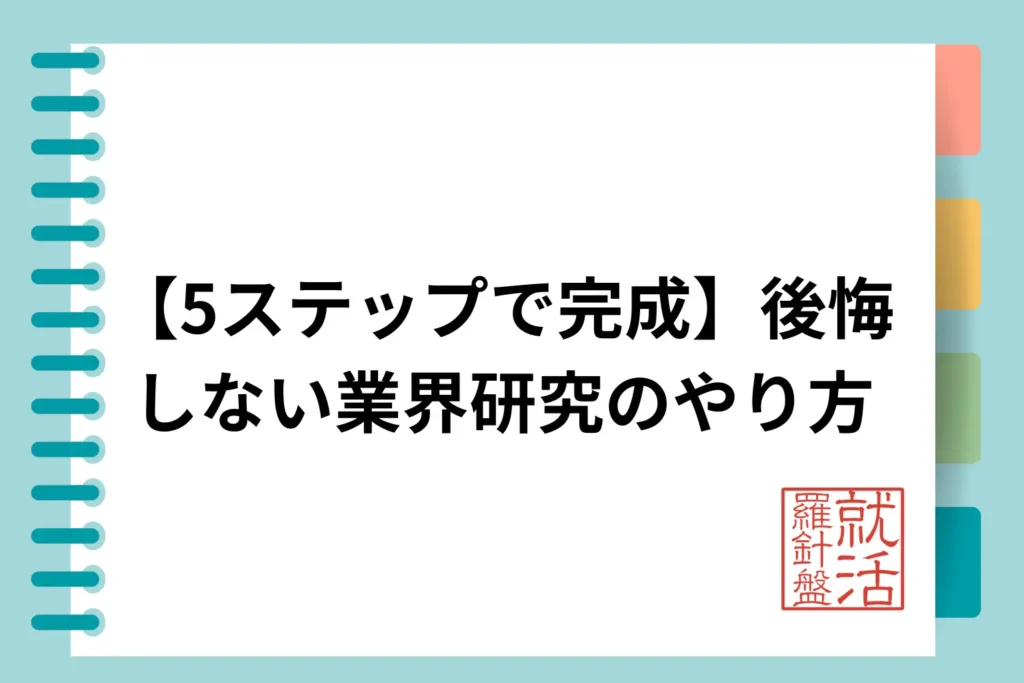
 キャリまる
キャリまる業界研究は「正しい順番」で進めることが成功の鍵です。全体像を掴み、自分軸で3~5業界に絞り、統計やIR情報で深掘りし、比較・分析・アウトプットまでを行うことで、一貫性のある志望動機が完成します。
全体→軸→深掘り→比較→ノート化の順が最も効率的。
一次情報(官公庁・IR)を基に分析。
OB訪問で定性情報を補完するのがベスト。
目的を理解したところで、いよいよ具体的な業界研究の進め方を見ていきましょう。ここでは、内定者が実践してきた王道の5ステップを紹介します。この順番で進めれば、誰でも効率的かつ効果的に業界研究を進めることができます。
【ステップ1】世の中にある業界の全体像をざっくり掴む
まずは、いきなり特定の業界を深掘りするのではなく、世の中にどのような業界が存在するのか、全体像を広く浅く把握することから始めましょう。この段階では、各業界の細かいビジネスモデルまで理解する必要はありません。「メーカー」「商社」「金融」「IT」など、どんな分類があり、それぞれが社会でどんな役割を果たしているのかを大まかに掴むのが目的です。
このステップでおすすめなのが『就職四季報』の業界地図ページや、『業界地図』といった書籍です。各業界の関連性や市場規模が図解されており、視覚的に全体像を理解するのに役立ちます。まずは本屋でパラパラとめくってみるだけでも、新たな発見があるはずです。
【ステップ2】「自分だけの軸」で興味のある業界を3〜5つに絞る
業界の全体像が見えてきたら、次は自己分析の結果と照らし合わせながら、興味のある業界を3〜5つ程度に絞り込んでいきます。ここで重要なのが、「自分だけの企業選びの軸」を持つことです。
「成長している業界で働きたい」「社会貢献性の高い仕事がしたい」「プライベートを大切にできる働き方がいい」など、あなたが仕事に求める価値観を明確にしましょう。この軸がないまま業界を選んでしまうと、情報収集の段階でブレてしまい、結局どの業界も魅力的に見えて決めきれなくなってしまいます。自己分析で見えてきた自分の強みや価値観を元に、仮説を立てて業界を絞ることが大切です。
【ステップ3】絞った業界を徹底的に深掘りする
業界をいくつかに絞ったら、いよいよ本格的な深掘りに入ります。ここでは、客観的なデータとリアルな情報の両面から、業界の解像度を徹底的に上げていきましょう。具体的には、以下の項目について調べていきます。
- 市場規模・動向: その業界は成長しているのか、縮小しているのか。
- ビジネスモデル: 誰に、何を、どのように提供して利益を上げているのか。
- 主要企業: 業界のトッププレイヤーはどこか。各社の力関係は?
- 課題と将来性: 今後どんな変化が予測されるか(技術革新、法改正など)。
- 働き方・キャリア: 平均年収、労働時間、求められるスキルなど。
情報収集には、以下のようなツールや情報源を活用するのがおすすめです。
| 情報収集ツール・ソース | 特徴・見るべきポイント |
|---|---|
| 会社四季報 業界地図 | 業界の全体像、企業間の関係性、最新トレンドを視覚的に把握できる。最初の1冊に最適。 |
| 就職四季報 | 給与、離職率、有給取得日数など、企業の「リアルな働き方」に関するデータが豊富。 |
| 企業の採用サイト・IR情報 | 事業内容や理念はもちろん、投資家向けのIR情報(決算短信、有価証券報告書)は事業の強みやリスクを客観的に知る上で非常に有益。 |
| ニュースサイト・専門誌 | 日経電子版やNewsPicks、業界専門メディアで最新の動向や課題を追う。 |
| 官公庁の統計データ | 経済産業省や総務省が公開するデータは、信頼性が高く、マクロな視点での業界分析に役立つ。 |
| OB/OG訪問 | 実際にその業界で働く先輩から、Webだけでは得られないリアルな情報を聞くことができる最も貴重な機会。 |
【ステップ4】同じ業界内の企業を比較・分析する
業界の全体像が見えたら、次は業界内の個別の企業に目を向け、比較・分析を行います。同じ業界に属していても、企業によって強みや社風、戦略は大きく異なります。「なぜA社ではなく、B社なのか」を自分の言葉で説明できるようになることが、このステップのゴールです。
比較する際は、以下のような項目で表を作成すると、違いが明確になり整理しやすくなります。
| 比較項目 | 分析の視点 |
|---|---|
| 事業内容・主力商品 | どの事業領域に強みを持っているか?収益の柱は何か? |
| 業績・財務状況 | 売上高、営業利益、成長率はどうか?安定しているか? |
| 企業理念・ビジョン | どのような価値観を大切にしているか?自分の価値観と合うか? |
| 社風・文化 | 社員の雰囲気は?挑戦的か、堅実か?(OB/OG訪問や説明会で探る) |
| 働き方・福利厚生 | 残業時間、転勤の有無、給与水準、研修制度などはどうか? |
| 今後の戦略 | 中期経営計画などで、今後どの分野に注力しようとしているか? |
この比較分析を通して、各社の特徴や違いが浮き彫りになり、自分の志望順位も明確になっていくはずです。
【ステップ5】調べた情報を「自分の言葉」でまとめる(業界研究ノートの作成)
最後のステップは、これまでに調べてきた情報を「自分の言葉で」アウトプットすることです。情報を集めただけで満足せず、自分なりに解釈し、整理してノートにまとめる作業が不可欠です。この「自分の言葉でまとめる」プロセスを通じて、知識が定着し、面接でスラスラと話せるようになります。
ノートには、調べた事実だけでなく、「この業界の課題に対して、自分の〇〇という強みを活かして貢献できそうだ」「A社の〇〇というビジョンに共感した」といった、自分の考えや感想を必ず書き加えるようにしましょう。これが、あなただけのオリジナルな志望動機を生み出す源泉となります。
参考
- 総務省「産業構造統計」
- 経済産業省「産業構造ビジョン2024」
- 東洋経済『業界地図2025』
 キャリまる
キャリまるステップ例:
①『業界地図』で全体を把握
② 自己分析で興味業界を3つに絞る
③ 総務省 統計局で市場データ収集
④ IR情報で各社の特徴を比較
⑤ NotionやExcelで整理・反省
この順に進めれば効率よく業界解像度が上がります。
【テンプレート配布】内定者が本当に使った業界研究ノート術
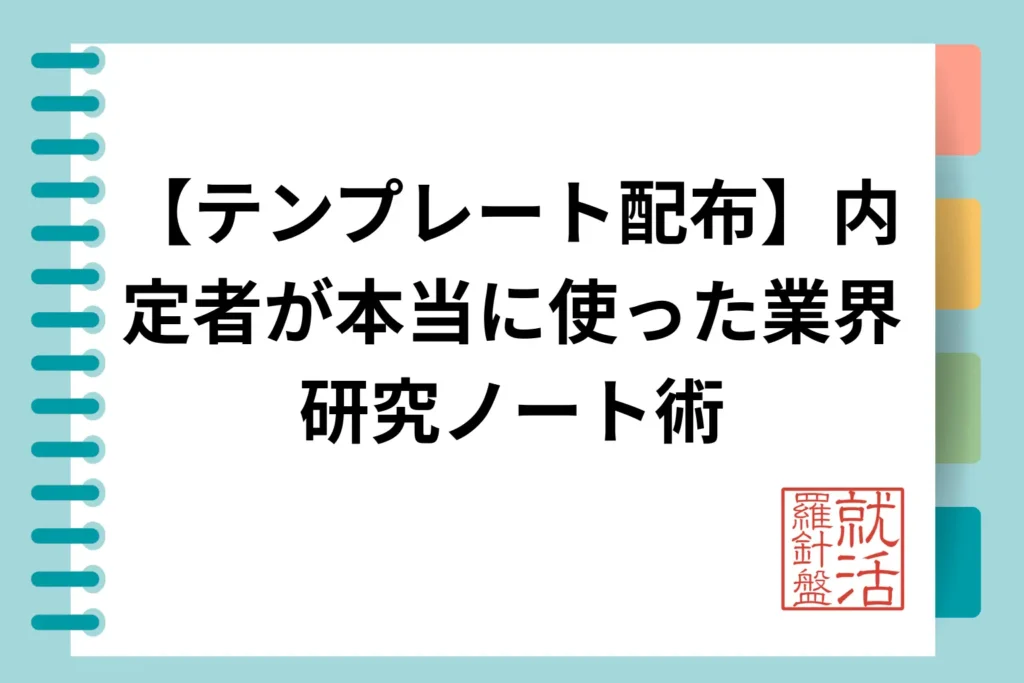
 キャリまる
キャリまる業界研究ノートは、単なるメモではなく「思考の可視化ツール」です。Fact(事実)とOpinion(自分の考え)を明確に分け、図表・比較を活用することで、思考が整理され面接で話せる知識になります。
「事実」と「意見」を分けて書くと整理しやすい。
図解・色分けで思考を可視化する。
自己分析との紐づけで一貫性を持たせる。
「ノートのまとめ方がわからない」「どんな項目を整理すればいいの?」という声にお応えして、この章では、面接で評価される業界研究ノートの作り方と、すぐに使えるテンプレートを紹介します。ただ情報を書き写すのではなく、「使える」ノートを作成しましょう。
差がつく業界研究ノートの3つのポイント
内定者のノートには、いくつかの共通点があります。以下の3つのポイントを意識するだけで、あなたの業界研究ノートの質は格段に向上します。
- 「Fact(事実)」と「My Opinion(自分の考え)」を分けて書く: 市場規模やビジネスモデルといった客観的な事実と、それに対する自分の考えや疑問を分けて記述しましょう。これにより、思考が整理され、面接で「あなたはどう思う?」と聞かれた際にスムーズに答えられます。
- 図やグラフを活用する: 業界の勢力図やビジネスモデルのフローなど、文字だけでは分かりにくい情報は積極的に図解しましょう。視覚的に整理することで記憶に定着しやすくなります。
- 自己分析と紐づける: 「なぜこの業界に興味を持ったのか?」「この業界で自分のどんな強みが活かせるか?」といった問いを常にノートに書き出し、自己分析と業界研究を繋げる意識を持つことが重要です。
【実例紹介】内定者はノートに何を書いていた?
ここでは、実際に複数業界の内定者が作成したノートの一部を、許可を得て再現・紹介します。彼らがどのような視点で情報を整理し、思考を深めていったのか、ぜひ参考にしてください。
(例)総合商社内定者 Aさんのノート
Aさんは、各商社の事業セグメント別の利益構成比を円グラフでまとめ、強みを持つ領域を可視化していました。さらに、「非資源分野への投資を加速させている背景には、資源価格の変動リスクを抑える狙いがある。自分の挑戦心は、こうした新規事業開発のフェーズで活かせるのではないか」といったように、企業の戦略と自己PRを接続させていました。
(例)ITベンチャー内定者 Bさんのノート
Bさんは、SaaS業界のビジネスモデルを「The Model」の図を用いて整理。その上で、各社のKPI(重要業績評価指標)を比較し、「A社は顧客獲得コスト(CAC)の回収期間が短く、営業効率が高い。自分の課題解決能力を活かし、より効率的なマーケティング手法を提案したい」と、具体的な数値に基づいた企業分析と貢献イメージを記述していました。
すぐに使える!業界研究テンプレート(Notion/スプレッドシート)
「ノート術は分かったけど、自分で一から作るのは大変…」というあなたのために、コピーしてすぐに使える業界研究用のテンプレートを用意しました。Notion版とGoogleスプレッドシート版がありますので、使いやすい方をご利用ください。
このテンプレートには、これまで解説してきた「業界の基本情報」「企業比較」「自分の考え」などを書き込む欄が予め用意されています。このフレームワークに沿って情報を埋めていくだけで、自然と構造化された業界研究ノートが完成します。
記入例
| No | 項目名 | 説明 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| ① | 企業理念・ビジョン | 企業が掲げる目的・価値観・方向性 | 「人と技術で社会を支える」など |
| ② | 事業内容・ビジネスモデル | 主力事業・収益源・顧客層 | BtoB向け製造業、SaaS事業 など |
| ③ | 強み・弱み | 他社との比較優位・課題 | 強み:ブランド力/弱み:海外展開の遅れ |
| ④ | 競合他社 | 同業・代替業種の企業 | 競合:リクルート/マイナビ など |
| ⑤ | 社風・働く人 | 社員の特徴・雰囲気 | チームワーク重視・フラットな組織文化 |
| ⑥ | 求める人物像・採用方針 | 採用サイトや面接での傾向 | 主体性・チャレンジ精神重視 |
| ⑦ | 自分との接点 | 自分の経験や価値観との共通点 | 「学祭での企画経験が事業開発と親和」など |
| ⑧ | 疑問点・質問リスト | OB訪問・面接で深掘りしたい点 | 「中途社員と新卒社員の比率は?」など |
テンプレートの使い方は簡単です。まずは興味のある業界について1枚のシートを完成させることを目標に、ステップ3で紹介した情報源を活用しながら各項目を埋めてみてください。
参考
- リクルート「就職白書2024」
- Notion公式サイト
 キャリまる
キャリまるGoogleスプレッドシートまたはNotionで「業界概要」「主要企業」「課題」「自分の意見」を構造化しましょう。これにより、更新・共有が簡単になり、思考の定点観測が可能です。参考としてリクルート 就職白書2024を読むと、内定者の分析法が理解できます。
【一覧】主要12業界の特徴と「自分軸」での選び方
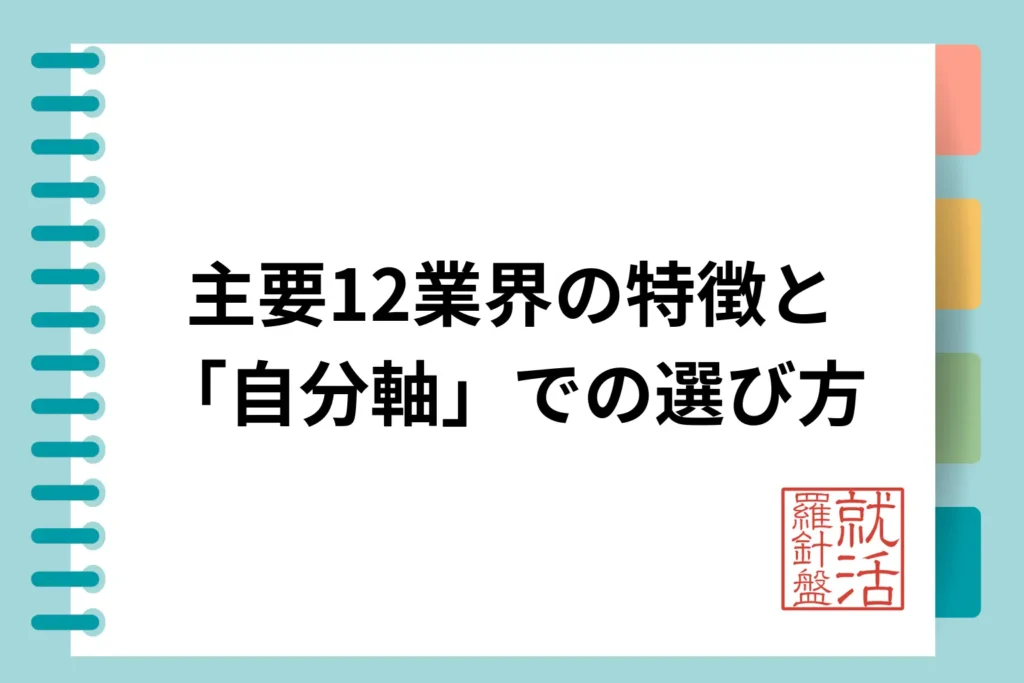
 キャリまる
キャリまる主要12業界(メーカー・商社・金融・IT・人材・コンサル・小売・サービス・不動産・マスコミ・医療福祉・官公庁)は、それぞれが異なる社会的使命とキャリア特性を持ちます。大切なのは「成長性」「安定性」「社会貢献性」など、自分が重視する軸で優先順位をつけること。人気だけでなく、働きがいや価値観との一致度を基準に選ぶのが成功の近道です。
就活人気業界12分類は“入口”であり、“答え”ではない。
「どの業界が良いか」より「自分が何をしたいか」を軸に判断。
メガトレンド(AI・脱炭素・高齢化)を軸に将来性を比較。
世の中には無数の業界がありますが、ここでは就活生に人気の主要な12業界をピックアップし、その特徴を簡単に紹介します。ただし、大切なのはこの中から選ぶことではなく、あくまで「自分軸」で業界を見る視点を持つことです。
これだけは押さえたい!主要12業界マップ
まずは代表的な業界とその特徴を一覧で見てみましょう。興味を持つきっかけとして活用してください。
| 業界分類 | 主な業界 | 特徴 |
|---|---|---|
| メーカー | 自動車、電機、食品、化学 | モノづくりを通じて社会に貢献。研究開発から営業まで職種が幅広い。 |
| 商社 | 総合商社、専門商社 | 「ラーメンから航空機まで」幅広い商材を扱う。グローバルな活躍の機会が多い。 |
| 小売 | 百貨店、スーパー、コンビニ | 消費者に最も身近な存在。店舗運営やマーケティング、商品開発などを担う。 |
| 金融 | 銀行、証券、保険 | お金を通じて経済を支える。高い専門性と倫理観が求められる。 |
| サービス・インフラ | 鉄道、航空、電力、ガス | 社会生活に不可欠な基盤を提供。安定性が高く、社会貢献性を感じやすい。 |
| ソフトウェア・IT | SIer、Webサービス、通信 | 情報技術で社会の課題を解決。急速な成長を続けており、変化が激しい。 |
| マスコミ | テレビ、新聞、広告、出版 | 情報を発信し、世論や文化を形成する。影響力が大きい一方、競争も激しい。 |
| 建設・不動産 | ゼネコン、デベロッパー | 街づくりやインフラ整備を担う。プロジェクトの規模が大きく、達成感がある。 |
| コンサルティング | 戦略、IT、人事 | 企業の経営課題を解決する専門家集団。論理的思考力と激務が特徴。 |
| 人材 | 人材紹介、人材派遣 | 「働く」を支援し、企業と人の成長に貢献する。コミュニケーション能力が重要。 |
| 医療・福祉 | 製薬、医療機器、介護 | 人々の生命や健康を支える。高い専門知識と使命感が求められる。 |
| 官公庁・団体 | 国家公務員、地方公務員 | 公共の利益のために働く。営利を目的とせず、国民全体の奉仕者となる。 |
業界の「将来性」を見極める3つの視点
どの業界で働くかを考える上で、「将来性」は非常に重要な指標です。将来性を見極めるには、以下の3つの視点を持つと良いでしょう。
- 市場の成長性: その業界の市場規模は拡大していますか?今後、人々の生活や社会にとって、その業界の重要性は増していくでしょうか。例えば、AIや脱炭素、高齢化社会といったメガトレンドに関連する業界は、将来性が高いと言えます。
- 代替リスクの低さ: その業界の提供する価値は、新しい技術やサービスによって簡単に代替されるものではないですか?人間にしかできない付加価値を提供できる業界は、長く生き残る可能性が高いです。
- 収益構造の安定性: 景気の波に左右されにくいビジネスモデルを持っていますか?インフラ業界のようなストック型のビジネスは、不況時でも安定した収益が見込めます。
「働きがい」を重視するなら?チェックすべきポイント
給与や安定性だけでなく、「働きがい」を重視する学生も増えています。働きがいを判断するためには、企業の「人」に対する姿勢を見ることが重要です。
例えば、社員の成長を支援する研修制度が充実しているか、多様なキャリアパスが用意されているか、社員の挑戦を後押しする文化があるか、といった点を確認しましょう。これらの情報は、採用サイトの社員インタビューや、OB/OG訪問で直接質問することで、よりリアルな実態を知ることができます。福利厚生だけでなく、社員への投資を惜しまない企業こそ、働きがいのある環境と言えるでしょう。
自己分析の結果を業界選びに活かす方法
業界研究と自己分析は、就職活動の両輪です。自己分析で見えてきたあなたの「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「価値観(Values)」を、業界選びに繋げましょう。
例えば、「チームで大きな目標を達成することに喜びを感じる(強み・価値観)」のであれば、大規模なプロジェクトが多い建設業界や総合商社が向いているかもしれません。「地道な分析と改善を繰り返すのが得意(強み)」であれば、データ分析が重要なマーケティング業界や金融業界で力を発揮できる可能性があります。このように、自分の特性と業界の特性をマッチングさせることで、納得感のある業界選びが可能になります。
参考
- 経済産業省「産業構造ビジョン2024」
- https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/
- マイナビ「業界研究大百科」
- https://job.mynavi.jp/conts/2025/tok/industry/
- 東洋経済『業界地図2025』
- https://str.toyokeizai.net/books/9784492976747/
 キャリまる
キャリまる『東洋経済 業界地図2025
』や『マイナビ業界研究大百科
』を使って、主要業界を俯瞰しましょう。特に理系は「専門分野×成長市場(例:素材×脱炭素)」、文系は「価値観×業務領域(例:挑戦×商社)」のように組み合わせ分析を行うと、自分に合う業界が浮かび上がります。
業界適性診断(AI職種・志望動機提案付き)
あなたの性格・価値観から、向いている業界と職種をAIが提案します。
【失敗から学べ】業界研究でやりがちなNG例
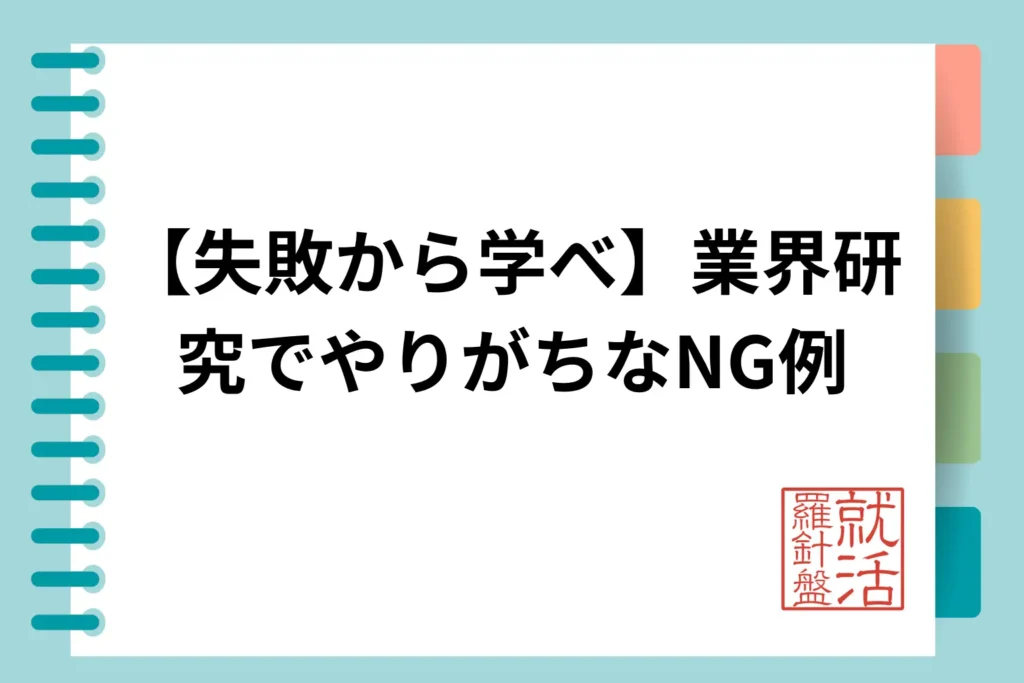
 キャリまる
キャリまる多くの就活生が「情報を集めただけ」で満足してしまいます。重要なのは、そこから何を考え、どう動くかです。理解を深めるために第三者に説明する練習を重ねると、知識が血肉になります。
まとめ病=理解の浅さ。
BtoC偏重=選択肢の狭さ。
情報メタボ=目的意識の欠如。
最後に、多くの就活生が陥りがちな業界研究の失敗例と、その対策について解説します。先輩たちの失敗から学び、効率的に就活を進めましょう。
やりがちな失敗例①:調べただけで満足してしまう「まとめ病」
最も多い失敗が、情報をノートに綺麗にまとめただけで満足してしまう「まとめ病」です。業界研究のゴールは、情報を整理することではなく、それをもとに「自分はどう考えるか」「自分ならどう貢献できるか」を語れるようになることです。
対策としては、必ずノートに「自分の意見」を書く欄を設けること。そして、友人やキャリアセンターの職員、OB/OGなど、第三者にその内容を話してみる機会を作りましょう。アウトプットを前提とすることで、インプットの質も向上します。
やりがちな失敗例②:大手有名企業しか見ない「BtoC偏重」
テレビCMなどでよく目にするBtoC(消費者向け)企業ばかりに目が行きがちですが、日本の優良企業の多くは、法人を相手にするBtoB企業です。特定の業界や有名企業に固執すると、自分に合う企業を見逃すことになります。
対策は、ステップ1で紹介した『業界地図』などを活用し、意識的に視野を広げることです。ある製品が消費者に届くまでには、素材メーカー、部品メーカー、製造装置メーカー、専門商社など、無数のBtoB企業が関わっています。そのサプライチェーンを辿ってみることで、知られざる優良企業に出会えるはずです。
やりがちな失敗例③:情報収集が目的化する「情報メタボ」
完璧を目指すあまり、あらゆる情報を集めようとしてしまい、結局消化しきれずに混乱してしまうのが「情報メタボ」状態です。全ての情報を網羅することは不可能ですし、その必要もありません。
対策は、「何のためにこの情報を調べるのか」という目的を常に意識することです。「志望動機を語るため」「企業の強みを理解するため」といった目的意識があれば、おのずと必要な情報とそうでない情報を見分けられるようになります。まずは仮説を立て、それを検証するために情報を集めるというスタンスが重要です。
参考
- 厚生労働省「キャリア形成支援ガイドライン」
- 経団連「採用指針2024」
 キャリまる
キャリまる毎週1回、友人やキャリアセンターで自分の業界研究を発表しましょう。人に説明することで知識が整理され、記憶にも定着します。厚労省のキャリア形成支援ガイドラインも、自己理解と社会理解の統合を推奨しています。
Q&A
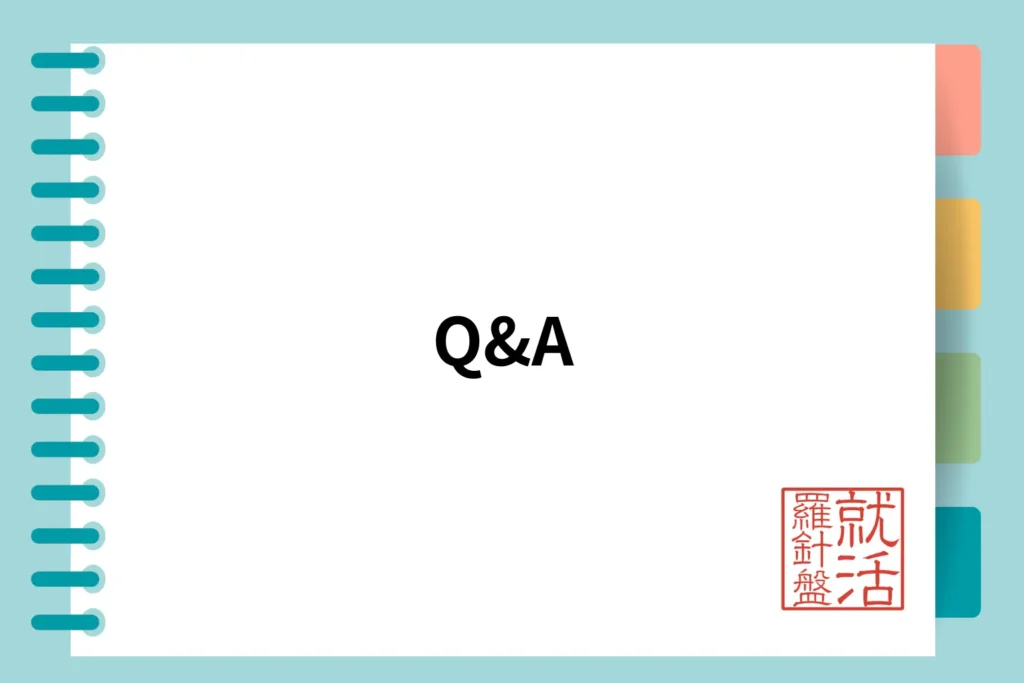
業界研究はいつから始めるべき?
短は「全体→自分軸→深掘り→比較→ノート化」。まず産業の全体像を掴み、自分の価値観で3〜5業界に絞る。官公庁統計と企業の一次情報(IR・有報)で深掘りし、比較表と“自分の意見”欄を作れば、ES/面接で一貫した志望動機に直結します。
エビデンス
- 経済産業省 産業構造ビジョン https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/
- 東洋経済『業界地図』 https://str.toyokeizai.net/books/9784492976747/
- 金融庁 EDINET(有価証券報告書)https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/
対応策
産業全体を俯瞰(業界地図で素早く)
俯瞰→優先順位の仮説を立てやすい
3〜5業界へ絞る(自分軸で選定)
価値観・強みと業界特性を照合
一次情報で深掘り(統計×IR)
数字と事実で思い込みを矯正
「信頼できる一次情報」はどこを見る?
マクロはe-Stat/総務省統計、業界別は経産省の各統計、企業は有価証券報告書・決算短信・適時開示が一次情報。採用・就活制度は文科省/経団連。これらを基準に、ニュースやSNSは“裏取り用”に回すのが安全です。
エビデンス
- e-Stat(政府統計)https://www.e-stat.go.jp/
- 総務省 統計局 https://www.stat.go.jp/
- 経産省 統計一覧 https://www.meti.go.jp/statistics/
- EDINET https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/
- JPX 適時開示 https://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html
対応策
e-Statで基礎統計を確認
市場規模や成長率の土台を把握
経産省の業界統計に当たる
業界ごとの構造・指標を補強
企業の有報/短信を精読
セグメント利益・リスクを確認
企業比較は何を指標にすれば良い?
「成長性(売上/営業益CAGR)」「収益性(営業利益率/ROIC)」「安定性(営業CF/自己資本比率)」「戦略(中計/投資領域)」「人的指標(離職・賃金)」の5群で比べるとズレにくい。全て一次情報に紐づけ可能です。
エビデンス
- EDINET(有報)https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/
- JPX 適時開示 https://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html
- 厚労省 就労条件総合調査 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/27-3.html
対応策
有報で財務KPIを統一取得
指標定義を揃え比較可能にする
中計で注力分野を確認
将来の収益源と投資意図を把握
労働指標を公的統計と整合
業界平均と企業値の差を評価
業界の「将来性」はどう見極める?
①市場の伸び(統計・白書)②規制/技術トレンド(白書・政策)③代替リスクと参入障壁(産業分析)の3視点で判定。情報通信白書や経産省ビジョンは、メガトレンド(AI/脱炭素/高齢化)の影響を体系的に確認できます。
エビデンス
- 総務省 情報通信白書 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/
- 経産省 産業構造ビジョン https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/
対応策
白書でメガトレンド把握
中長期の需要/供給構造を確認
統計で実数の伸びを検証
CAGRなど定量で“伸び”を
規制・技術の変化を点検
追い風/逆風を早期に察知する
志望動機に“深み”を出す書き方は?
「業界課題(一次情報)→自分の経験/強み→入社後の貢献提案」の三段構成。“好き”ではなく“課題に対する解決意欲”を示すと評価が安定。厚労省ガイドラインが示す“自己理解×社会理解の統合”を実践形に落とし込みます。
「業界課題(一次情報)→自分の経験/強み→入社後の貢献提案」の三段構成。“好き”ではなく“課題に対する解決意欲”を示すと評価が安定。厚労省ガイドラインが示す“自己理解×社会理解の統合”を実践形に落とし込みます。
エビデンス
対応策
一次情報で業界課題を定義
事実ベースで論点を設定する
自分の強みを課題に接続
再現性ある行動特性で語る
具体的な貢献アイデア提示
3〜5年のアクショ
OB/OG訪問で“聞くべき核心”は?
HPに無い“現場の優先指標・評価軸・失敗事例”が核心。日/週の時間配分(内勤/外勤/会議/制作)と成果が出た再現可能な行動を具体で聞くと、働き方と適性が一気に解像度UP。訪問は大学キャリア/就活サイト経由が安全です。
エビデンス
- マイナビ OB・OG訪問ガイド https://job.mynavi.jp/conts/2025/obog/
対応策
事前仮説を3点用意
想定と差分が浮き彫りになる
行動レベルで深掘る
何を/どれくらい/どう工夫
記録→ノートへ反映
志望動機に即日反映する
文系/理系で業界研究のコツは違う?
根本手順は同じ。ただし理系は専門×成長市場の掛け算(例:材料×脱炭素、データ×医療)で強みを尖らせる。文系は価値観×業務領域(例:挑戦×商社、安定×インフラ)で選定。内定者の傾向は就職白書の実データが参考になります。
エビデンス
- リクルート 就職白書 https://www.recruit.co.jp/
対応策
自分軸(価値観/強み)を定義
判断基準を先に固定化する
業界×自分軸の組合せ表
相性の良い領域が見える化
白書データで妥当性確認
客観データで補正をかける
いつから何をやれば間に合う?(時期別)
目安は3年夏前に着手。夏インターン前に「全体→絞り込み」を終えると加速。広報/選考の公式スケジュール(広報3/1、選考6/1※年度通知参照)は文科省の要請を必ず確認し、逆算で計画を組むのが安全策です。
エビデンス
- 文科省 就職・採用活動に関する要請 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shusyoku/1400668.htm
- 経団連 採用活動に関する指針 https://www.keidanren.or.jp/policy/
対応策
3年春:全体把握&自分軸
夏インターン応募に間に合う
夏:深掘り&OB/OG訪問
早期選考ルートの可能性あり
秋冬:比較・志望動機完成
3/1広報に合わせ最終整備
まとめ:業界研究は「未来の自分」への最高の投資
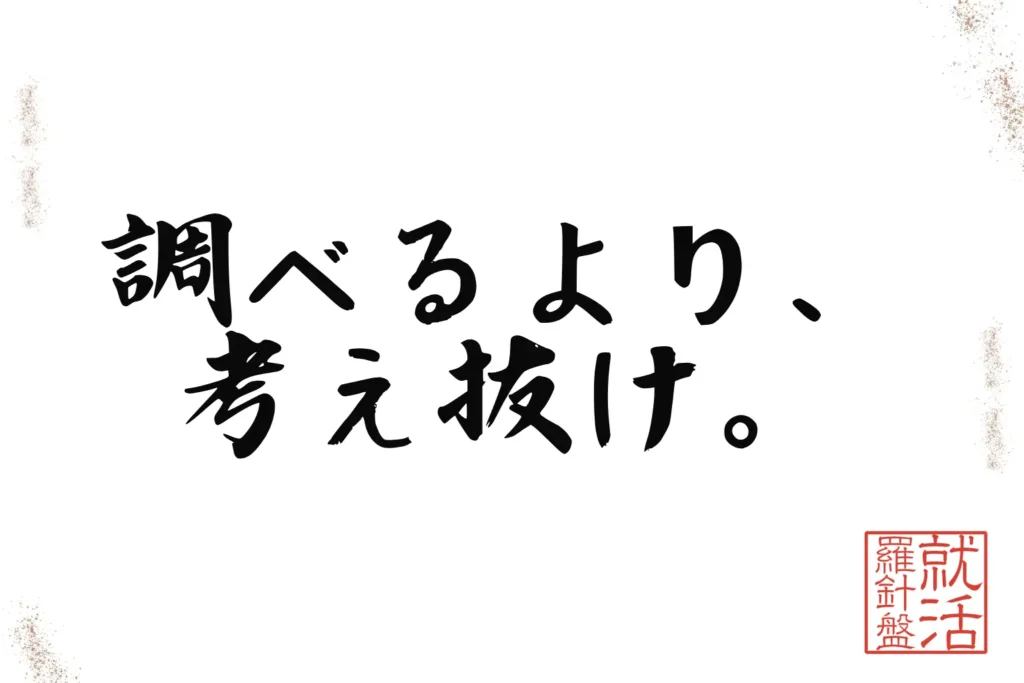
本記事では、後悔しないための業界研究のやり方を、目的の理解から具体的な5ステップ、内定者のノート術、失敗例まで網羅的に解説しました。
業界研究は、単なる就活のタスクではありません。それは、世の中の仕組みを理解し、その中で自分がどう生きていきたいかを考える、未来の自分への最高の投資です。業界の解像度を上げることで、あなたは自信を持って面接に臨めるだけでなく、入社後も納得感を持ってキャリアを歩むことができます。
まずは配布したテンプレートを使い、今日から気になる業界を1つ調べてみましょう。その小さな一歩が、あなたの「後悔しない企業選び」に繋がるはずです。あなたの就職活動が、実りあるものになることを心から応援しています。
 キャリまる
キャリまる業界研究は、未来の自分に投資する時間です。焦って多くを調べるより、1業界を深く理解することが成果に直結します。まずは興味のある1業界を選び、『業界地図』を片手に情報を整理。次に、その業界で「自分は何をしたいのか」を書き出しましょう。思考を文字にすることで、自己分析と業界理解が繋がり、説得力ある志望動機が生まれます。
出典URL一覧
- 経済産業省「産業構造ビジョン2024」:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/
- 厚生労働省「キャリア形成支援ガイドライン」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183343.html
- マイナビ2025 就職白書:https://job.mynavi.jp/2025/
- 東洋経済『業界地図2025』:https://str.toyokeizai.net/books/9784492976747/
- 総務省「統計局データ」:https://www.stat.go.jp/data/
- 経団連「採用指針2024」:https://www.keidanren.or.jp/policy/