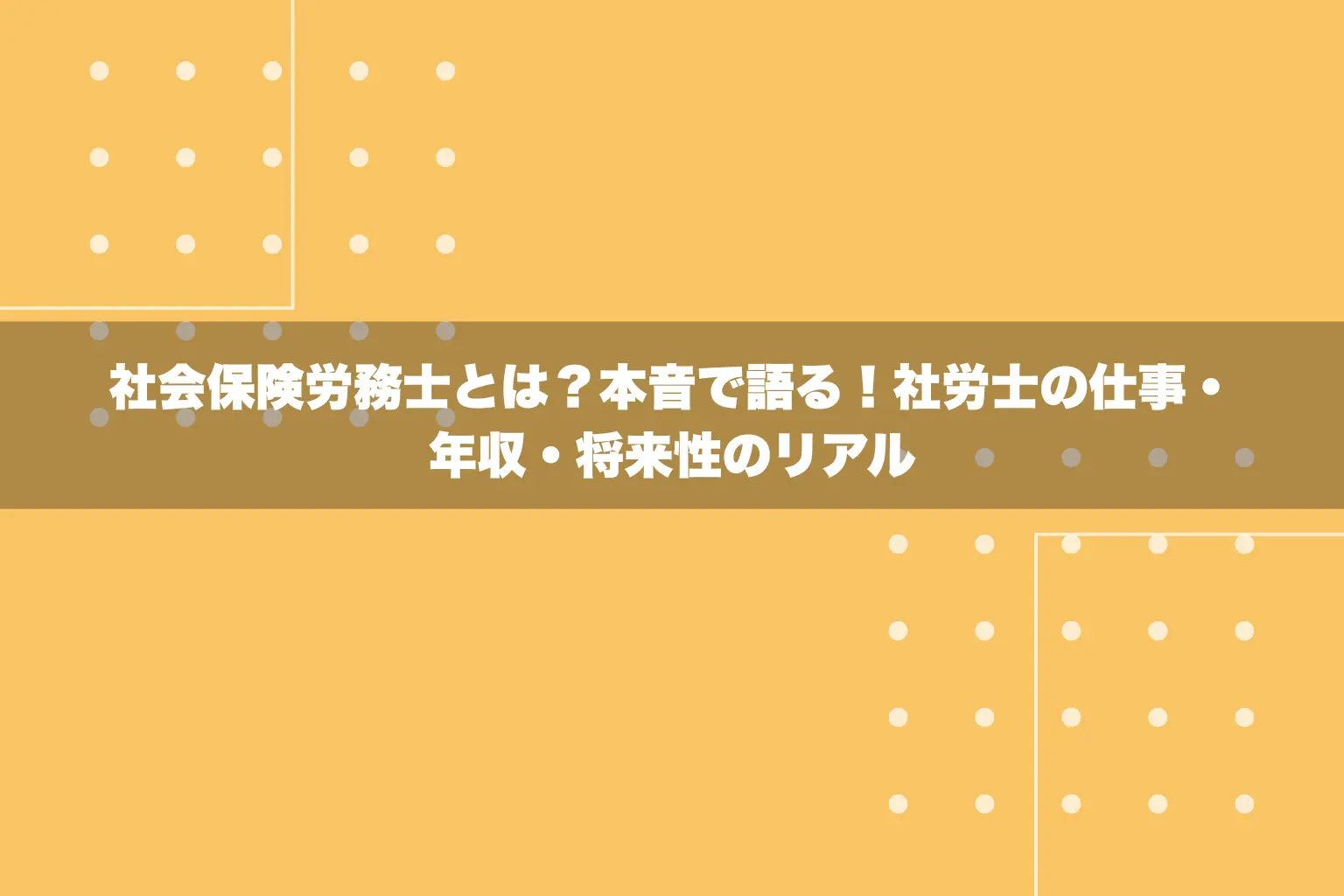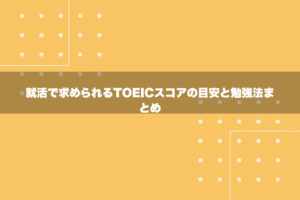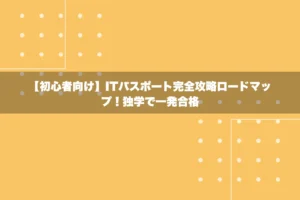「今の仕事、このままでいいのかな…」「専門スキルを身につけて、もっと安定した将来を築きたい」
そんな風にキャリアについて悩んでいるとき、「社会保険労務士(社労士)」という資格が選択肢に浮かぶことがあるかもしれません。しかし、具体的にどんな仕事で、本当に稼げるのか、試験はどれほど難しいのか、リアルな情報がわからず一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、現役社労士が、そんなあなたの疑問や不安に本音でお答えします。社労士の基本的な仕事内容から、誰もが気になる年収の実態、独立と勤務のメリット・デメリット、そして「AIに仕事は奪われる?」といった将来性まで、徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、社労士という仕事の理想と現実が明確になり、あなたが本当に目指すべき道なのかを判断できるようになっているはずです。さあ、後悔しないキャリア選択のために、まずは「リアル」を知ることから始めましょう。
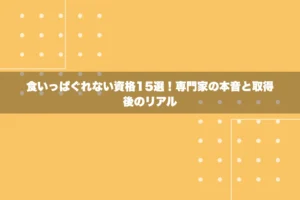
- 社労士は「人」に関するプロ。法律・手続き・労務相談が主な仕事
- 1号・2号・3号の独占業務があり、国家資格として信頼性が高い
- 勤務で安定、独立で自由と高収入。自分に合った働き方が選べる
- AIには奪われない「複雑な労務対応」や「人の感情に寄り添う力」が必要
- 試験は難関(合格率6〜7%)だが、過去問中心の戦略学習で突破可能
社会保険労務士(社労士)は、企業の「人」に関する法律や手続きを専門に扱う国家資格。労務の手続き代行や書類作成だけでなく、近年ではハラスメント対応や働き方改革などのコンサルティング業務も増加中。勤務社労士なら安定収入、独立開業なら高収入も狙える。AIの台頭に不安を抱かれがちだが、人間にしかできない仕事の価値がむしろ高まっているのが現実。試験は難関だが、しっかり対策すれば十分合格可能!
社会保険労務士(社労士)とは?「人」に関する専門家
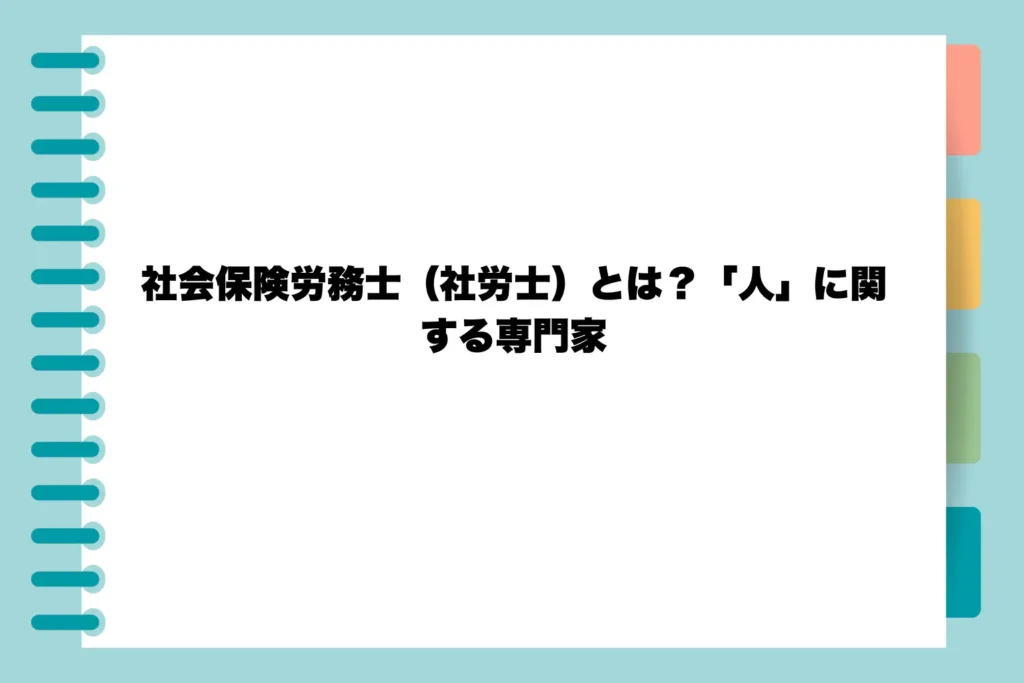
 キャリまる
キャリまる企業の“人の悩み”を解決するお助けマン!
社会保険労務士(社労士)とは、一言でいえば「企業における『人』に関する専門家」です。労働・社会保険に関する法律の専門家として、企業経営に不可欠な「人材」に関する課題を解決し、企業の健全な発展と、そこで働く人々の福祉向上をサポートする国家資格者です。
「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室①
「社労士って、正直どんな仕事なんですか?」
 優菜さん
優菜さんキャリまるさん〜、最近“社労士”ってよく聞くんですけど、正直、何する仕事かピンとこなくて…。なんか法律っぽいイメージはあるんですけど…
 キャリまる
キャリまるいい質問!簡単に言うと、“人と会社を法律でつなぐ専門家”って感じかな。会社で働く人たちの雇用とか労働環境、社会保険の手続きなんかを支えてるんだよ。
 優菜さん
優菜さんへぇ…会社の“人事部門の外部サポート”みたいな感じですか?
 キャリまる
キャリまるまさにそれ!会社の“働く人”に関するルールとかトラブルに対して、専門知識でアドバイスしたり書類を作ったりして、企業と社員の“橋渡し”をしてるのが社労士
社労士の3つの独占業務(1号・2号・3号業務)
社労士の仕事は多岐にわたりますが、特に法律で社労士にしか許可されていない「独占業務」が3つあります。これらが社労士の専門性の根幹をなしており、1号・2号・3号業務と呼ばれています。
| 業務区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号業務 | 手続き代行 | 労働社会保険の加入・脱退手続き、労災の給付申請、助成金の申請書類作成・提出 |
| 2号業務 | 帳簿書類の作成 | 労働者名簿、賃金台帳、就業規則などの作成 |
| 3号業務 | コンサルティング | 人事・労務管理に関する相談・指導(紛争解決手続代理業務を含む特定社労士のみ) |
1号業務:行政機関への手続き代行
1号業務は、企業に代わって行政機関へ提出する書類の作成や申請を代行する仕事です。例えば、従業員の入社・退社に伴う健康保険や厚生年金保険の資格取得・喪失手続き、業務中の事故に対する労災保険の給付申請などがこれにあたります。
これらの手続きは複雑で法改正も多いため、専門知識を持つ社労士が代行することで、企業は本業に専念できるのです。
2号業務:法律に基づく帳簿書類の作成
2号業務は、労働基準法などの法律で企業に作成・備え付けが義務付けられている帳簿書類を作成する仕事です。代表的なものに、「労働者名簿」「賃金台帳」「就業規則」があります。特に就業規則は、会社のルールを定める重要な書類であり、法改正に対応した適切な内容で作成・変更することが、労使トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
3号業務:人事・労務に関するコンサルティング
3号業務は、人事や労務管理に関する相談に応じ、専門的なアドバイスを行うコンサルティング業務です。働き方改革への対応、人事評価制度の構築、従業員のメンタルヘルス対策、ハラスメント問題への対応など、その内容は多岐にわたります。近年、企業の経営課題は複雑化しており、このコンサルティング業務の重要性が非常に高まっています。
 キャリまる
キャリまる「人と関わる仕事がしたい」「企業の役に立ちたい」人にピッタリ!「この資格じゃないとできない仕事がある」って強みになる!
- 手続き代行だけでなく「人事の相談役」にもなる
- 法律に基づいたアドバイスができるのが強み
- 労働者・経営者の両方に信頼される立場
- 1号(手続き)・2号(書類作成)・3号(コンサル)が三本柱
- 特定社労士になると“裁判外紛争”にも対応可能
「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室②
「“独占業務”って、社労士にしかできない仕事ってこと?」
 優菜さん
優菜さん調べたら“独占業務”って言葉が出てきたんですけど…それって何ですか?
 キャリまる
キャリまるうん、いいところに目をつけたね!社労士には“3つの独占業務”があるんだ。つまり社労士じゃないとできない仕事ってこと。① 行政手続きの代行(1号業務)② 帳簿や就業規則の作成(2号業務)③ 人事労務のコンサルティング(3号業務)がそれにあたる。
 優菜さん
優菜さんコンサルも業務なんですか!?もっと事務的な仕事だけかと思ってました!
 キャリまる
キャリまるそう思われがちだけど、実は“3号業務”がいま一番伸びてる領域なんだよ。ハラスメント相談、働き方改革、メンタルヘルス対応とか、企業からのニーズが増えててね。
行政書士との違いは?
 キャリまる
キャリまる「人」vs「許可申請」…専門分野が違うだけ!
社労士とよく比較される資格に「行政書士」があります。どちらも書類作成や手続き代行を行う専門家ですが、扱う分野が全く異なります。
簡単に言えば、社労士が「人」に関する手続きの専門家であるのに対し、行政書士は「許認可」に関する手続きの専門家です。例えば、飲食店の営業許可や建設業許可の申請は行政書士の業務範囲です。企業の労務と許認可の両方をサポートするために、ダブルライセンスを取得する人もいます。
 キャリまる
キャリまる「どんな分野の専門家になりたいか?」で選ぼう!
- 行政書士は許認可・契約関係が専門
- 社労士は労務・人事・社会保険が専門
- ダブルライセンスで幅広く活動する人も増加中
「社労士はやめとけ・意味ない」と言われる理由と現実
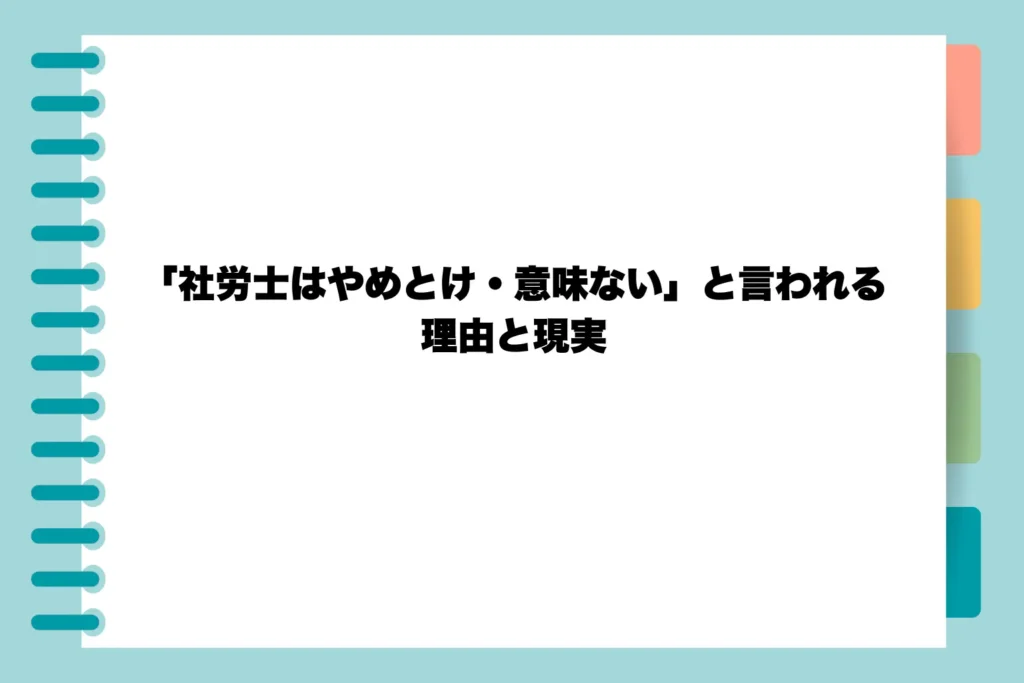
 キャリまる
キャリまる意味あるかは“使い方”次第。資格はスタートライン!
インターネットで検索すると「社労士はやめとけ」「意味ない」といったネガティブな意見を目にすることがあります。これらはなぜ言われるのでしょうか?主に以下の3つの理由が挙げられます。
- 試験が超難関なのに、すぐに稼げるわけではない: 合格率6〜7%の難関試験を突破しても、特に独立開業した場合、すぐに高収入が得られるわけではありません。営業力や経営手腕がなければ、顧客を獲得できず苦労するケースもあります。
- AIに仕事を奪われるという懸念: 1号・2号業務のような定型的な手続き・書類作成業務は、将来的にAIに代替される可能性が指摘されています。この点に不安を感じる人が多いようです。
- 実務経験が重視される世界: 資格を取得しただけでは、すぐにプロとして活躍できるわけではありません。特に企業の人事担当者などは、資格よりも実務経験を重視する傾向があり、「資格だけでは意味がない」と感じる場面があるかもしれません。
しかし、これらの意見は一面的な見方です。コンサルティング業務の需要は増え続けており、AIを使いこなして付加価値の高いサービスを提供できる社労士の価値はむしろ高まっています。重要なのは、こうした現実を理解した上で、戦略的にキャリアを築くことです。
 キャリまる
キャリまる「資格を活かす準備」が合格前から必要。計画的に動こう!
- 試験は難しいけど、合格後にどう活かすかが大事
- AIに代替されるのは「単純作業」、本質は対人支援
- 実務経験の有無が“稼げるかどうか”に直結
「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室③
「ネットで“やめとけ”って出てきたんですけど…」
 優菜さん
優菜さんちょっと検索したら“社労士はやめとけ”って記事が多くて…。正直、不安になってます…」
 キャリまる
キャリまるわかる、そのワード出てくるよね(笑)でも、それには理由があるの。①試験が難しいのに、資格を取ってもすぐには稼げない②1号・2号業務はAIに代替されるかもしれない③実務経験がないと“使えない資格”と言われがちなんかがよく言われる。
 優菜さん
優菜さん「うわ…リアル。でも、全部が“意味ない”ってわけじゃないですよね?
 キャリまる
キャリまるもちろん。むしろ、“戦略的に使えばめちゃくちゃ強い資格”だよ。AIにはできない“人の問題に寄り添う力”は、これからの社労士の大きな武器になる。
社労士のリアルな働き方と年収事情
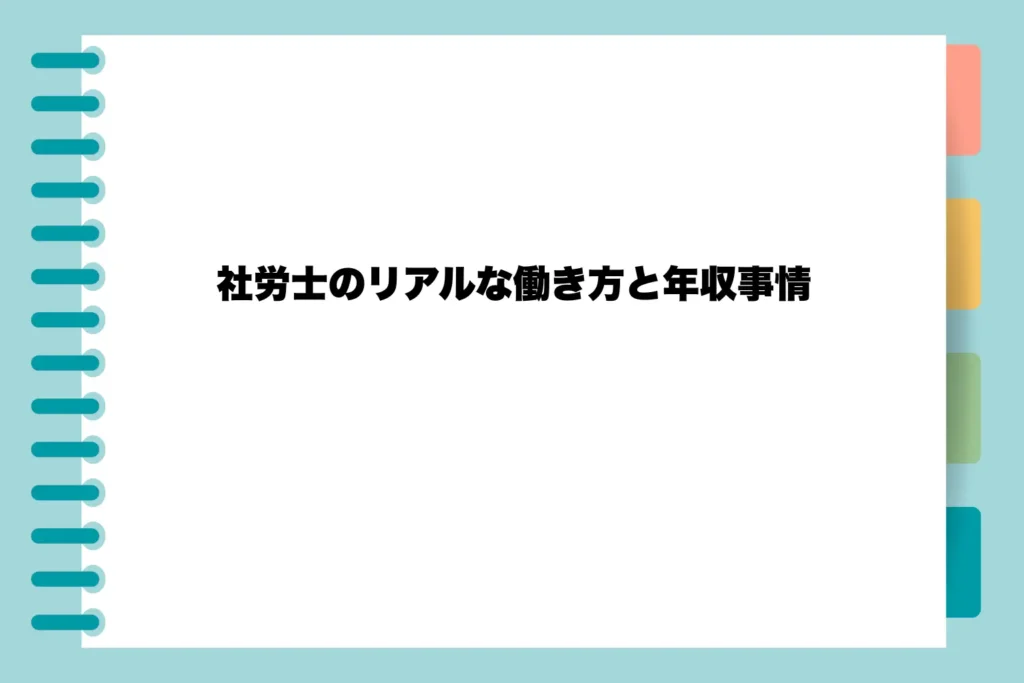
社労士の働き方は、大きく「勤務社労士」と「独立開業社労士」の2つに分かれます。どちらの道を選ぶかによって、仕事内容や年収、働き方の自由度は大きく異なります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、あなたに合ったキャリアパスを考えてみましょう。
 キャリまる
キャリまる安定か自由か、自分の人生に合った働き方が選べる!
勤務社労士:安定した環境で専門性を磨く
勤務社労士は、企業の人事・労務部門や、社会保険労務士法人(事務所)に所属して働きます。安定した収入と福利厚生のもとで、専門知識を深められるのが魅力です。
勤務社労士の仕事内容と年収
企業に勤務する場合、自社の人事制度の運用、給与計算、社会保険手続き、社員の労務相談対応などが主な業務です。労務のスペシャリストとして、経営陣と従業員の橋渡し役を担います。
年収は勤務先の規模や経験によって変わりますが、厚生労働省の統計などを参考にすると、平均的には450万円〜700万円程度がひとつの目安です。大手企業や管理職クラスになると、800万円以上を目指すことも可能です。
未経験からでも目指せる?
未経験から勤務社労士を目指すことは十分可能です。ただし、求人は経験者向けが多いのも事実。まずは一般企業の総務や人事部門で実務経験を積みながら資格取得を目指す、あるいは、資格取得後に未経験者可の社労士事務所やアウトソーシング会社でキャリアをスタートさせるのが現実的なルートです。
独立開業社労士:自由と高収入を目指す経営者
独立開業社労士は、自ら事務所を構え、複数の企業と顧問契約を結んだり、個別の相談を受けたりします。自分の裁量で仕事を進められる自由さと、成果次第で高収入を得られる可能性が最大の魅力です。
独立開業社労士の仕事内容と年収
主な収入源は、企業との顧問契約です。顧問先に対して、1号・2号業務の代行や、3号業務の継続的なコンサルティングを提供します。成功すれば年収1,000万円以上を稼ぐ社労士も少なくありませんが、収入は青天井であると同時に、顧客を獲得できなければ収入ゼロのリスクもあります。年収は100万円台から数千万円台まで、まさに経営手腕次第です。
独立のメリット・デメリット
独立には大きな可能性がありますが、リスクも伴います。以下の比較表で、自分にとってどちらが重要かを考えてみましょう。
| 項目 | 勤務社労士 | 独立開業社労士 |
|---|---|---|
| 収入 | 安定しているが上限あり | 不安定だが青天井の可能性 |
| 働き方 | 会社の規則に従う | 自由度が高い(時間・場所) |
| 業務内容 | 所属組織の業務が中心 | 自分で仕事を選べる |
| スキル | 専門知識、社内調整力 | 専門知識、営業力、経営スキル |
| リスク | 会社の業績や方針に左右される | 収入ゼロのリスク、全責任を負う |
| やりがい | 組織への貢献 | 顧客からの直接的な感謝、事業の成長 |
 キャリまる
キャリまるまずは「どっちのライフスタイルが合うか」を考えてみよう!
- 勤務社労士は会社勤めで安定+学べる
- 独立社労士は顧客開拓次第で高収入も可能
- 両者に必要なスキルが違う(勤務:調整力/独立:営業力)
「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室④
「勤務と独立ってどう違うんですか?」
 優菜さん
優菜さん就活生の立場から見て、社労士って“勤務”と“独立”どっちが現実的なんですか?
 キャリまる
キャリまる最初は勤務が現実的かな。たとえば企業の人事部に入るか、社労士事務所に就職して実務経験を積む。でも、将来“独立”って選択肢があるのが魅力的なところ。勤務社労士は、安定してて福利厚生もしっかり。年収は450~700万円くらいが目安。独立社労士は年収1,000万円以上も目指せるけど、自分で顧客を取る力が必要。
 優菜さん
優菜さんなるほど…!独立は憧れるけど、いきなりはちょっと不安ですね。
 キャリまる
キャリまるうん、“勤務→経験→独立”ってキャリアを描いてる人、多いよ。副業から始める人もいるし、柔軟な働き方ができるのは本当に魅力。
女性のキャリアとしての社労士
 キャリまる
キャリまる自分のペースで働けるから、ライフイベントと両立しやすい!
社労士は、女性にとっても非常に魅力的な資格です。産休・育休といった制度に精通しているため、自身のライフイベントにも知識を活かせます。また、独立開業すれば、育児や介護と両立しながら自宅で仕事を続けるなど、柔軟な働き方を選択しやすいのも大きなメリットです。実際に、多くの女性社労士が様々な分野で活躍しています。
 キャリまる
キャリまる「将来に備えて資格を取りたい」なら、社労士は心強い選択!
- 時間・場所に縛られにくい独立の道がある
- 出産・育児の制度に詳しいので“自分の人生にも使える”
- 働き方のモデルケースが多数あり、ロールモデルに出会える
「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室⑤
「女性に向いてるって聞いたけど、本当ですか?」
 優菜さん
優菜さんあと、SNSで“社労士は女性におすすめ”って書いてあるのを見たんですけど…本当ですか?
 キャリまる
キャリまるうん、それは間違いないよ。ライフイベントと両立しやすい専門職として、社労士はすごく人気があるんだ。
 優菜さん
優菜さんどういうところが働きやすいんですか?
 キャリまる
キャリまる例えば…
・育児や介護と両立できる柔軟な働き方(在宅・フリーランス)
・出産・育休・労働時間といった制度に詳しく、自分自身のライフプランにも活かせる
・実際に独立して活躍する女性社労士もどんどん増えてる
 優菜さん
優菜さんそれは心強いですね。仕事と人生、両方ちゃんと考えたいから…!
社労士の将来性|AIに仕事は奪われるのか?
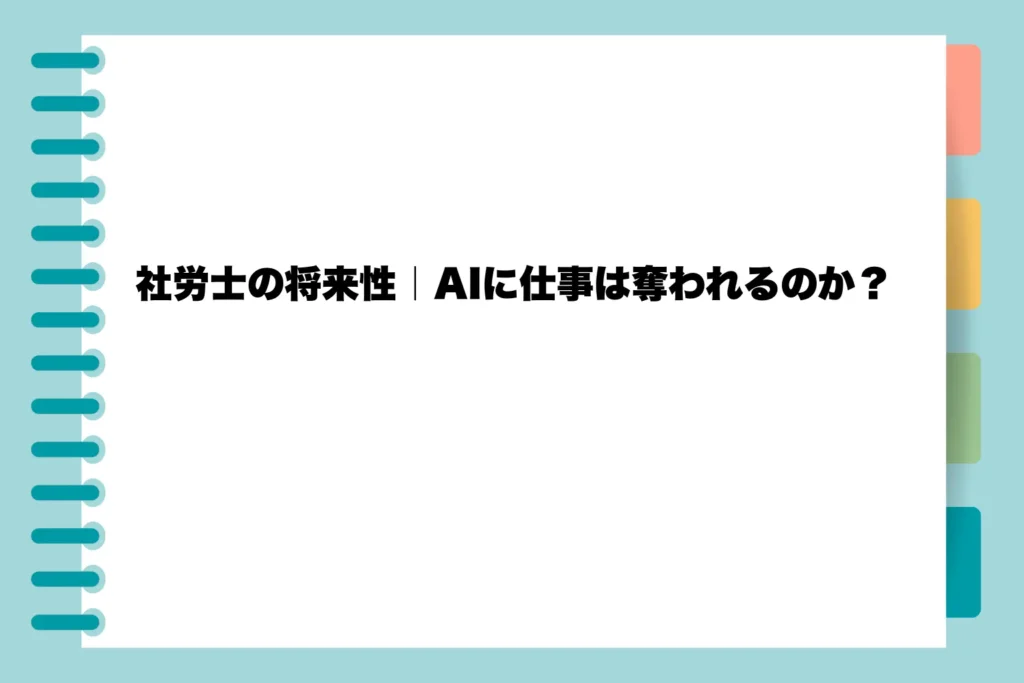
「AIの進化で社労士の仕事はなくなるのでは?」これは、社労士を目指す多くの人が抱く最大の不安かもしれません。結論から言えば、社労士の仕事が完全になくなることはありません。むしろ、AI時代だからこそ価値が高まる業務が存在します。
 キャリまる
キャリまるAIが苦手な“人と向き合う仕事”が社労士の出番!
AIに代替される業務とは?
たしかに、一部の業務はAIによって自動化・効率化が進むでしょう。具体的には、以下のような定型的な業務が該当します。
- 労働保険・社会保険の申請書作成: 従業員のデータに基づき、各種申請書を自動で生成する。
- 給与計算: 勤怠データを取り込み、自動で給与を計算し、明細書を発行する。
- 簡単な問い合わせ対応: 「有給休暇の残日数は?」といった定型的な質問にチャットボットが自動で回答する。
これらの業務は、これまで社労士の仕事の一部を占めていましたが、今後はAIツールを「使いこなす」側に回ることが求められます。事務作業から解放された時間を、より付加価値の高い業務に使うことが重要になります。
AI時代にこそ価値が高まる社労士の仕事
一方で、AIには代替できない、人間ならではのスキルが求められる業務の価値は飛躍的に高まります。
1. 複雑な労務問題への対応・コンサルティング
ハラスメント問題、メンタルヘルス不調者への対応、解雇を巡るトラブルなど、個別性が高く、法律知識だけでなくコミュニケーション能力や状況判断力が求められる問題解決は、AIには困難です。企業の状況や従業員の感情を汲み取り、最適な解決策を提案するコンサルティングは、まさに社労士の腕の見せ所です。
2. 戦略的人事制度の設計
企業の経営戦略と連動した人事評価制度や賃金制度を設計する仕事も、AIにはできません。企業のビジョンを理解し、従業員のモチベーションを高め、組織を成長させるための制度を構築するには、創造性や戦略的思考が不可欠です。
3. 法改正への迅速な対応と提案
労働関連法規は頻繁に改正されます。法改正の内容をいち早くキャッチし、その背景を理解した上で、顧問先企業にどのような影響があり、何をすべきかを具体的にアドバイスする役割は、今後も社労士に強く求められます。AIは情報を提供してくれますが、それをどう解釈し、どう企業に適用するかは専門家である人間の仕事です。
結論:AIを使いこなし、コンサル能力を磨く社労士が生き残る
これからの社労士は、AIを恐れるのではなく、業務を効率化するパートナーとして積極的に活用する姿勢が求められます。そして、AIによって生み出された時間を使って、人間でなければできない高度なコンサルティングスキルを磨き、顧客との信頼関係を深めていく。
これが、AI時代を生き抜く社労士の姿です。働き方の多様化や複雑な法改正が進む現代において、「人」の専門家である社労士の需要は、なくなるどころか、ますます高まっていくでしょう。
 キャリまる
キャリまる「AIと組んで働ける人」が今後は強い。恐れず使いこなそう!
- 書類作成はAIで効率化=むしろ“時間ができる”
- 人間関係の悩み・制度設計は人にしかできない
- 法改正を読み解く力は“人の判断力”がモノを言う
「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室
「AIで仕事がなくなるって言われてますけど…?」
 優菜さん
優菜さんあとちょっと怖いのが、“社労士の仕事はAIに奪われる”って噂です…
 キャリまる
キャリまるそれ、よくあるけど心配しすぎなくて大丈夫。確かに、書類作成とか定型業務はAI化される部分もあるよ。
 優菜さん
優菜さんじゃあ、社労士の仕事って減っていくんじゃ…
 キャリまる
キャリまるそれがね、逆に“AIにできないこと”の価値が上がるんだよ。
・人事トラブルやハラスメントの対応
・メンタルヘルスや働き方改革の提案
・人事制度や賃金体系の設計
 キャリまる
キャリまるこういう“感情や現場の空気”を読む力が必要な仕事は、むしろこれからの時代に求められる。AIはツール、社労士は“人間の専門家”として強くなっていくと思うよ。
 優菜さん
優菜さんなるほど…AIと戦うんじゃなくて、味方にすればいいんですね!
社労士になるには?試験の難易度と勉強法
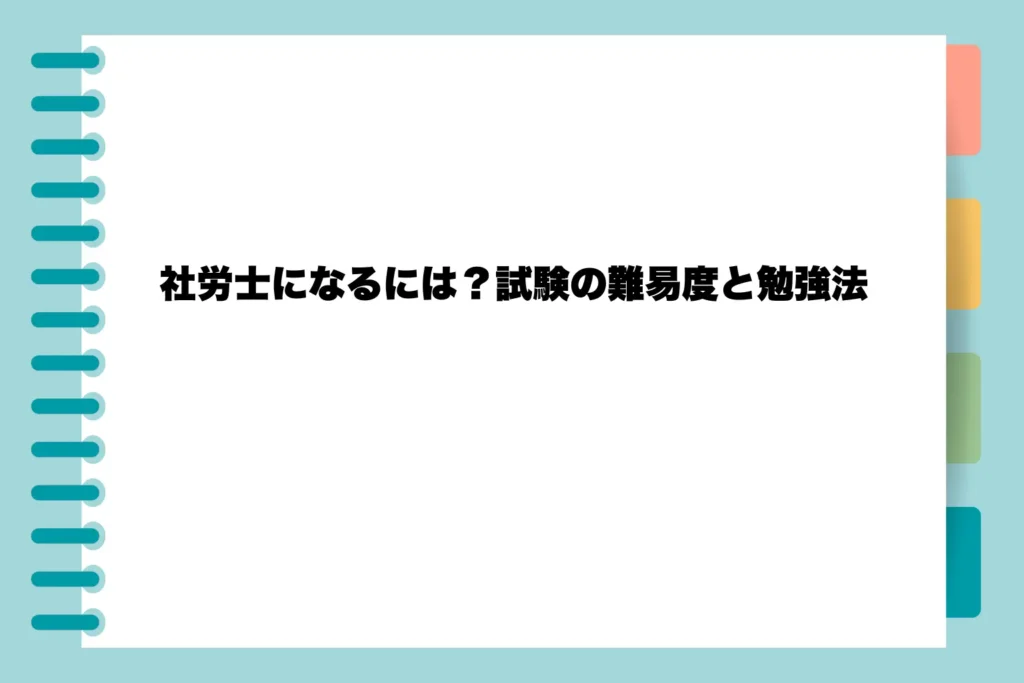
 キャリまる
キャリまるちょっと本気出せば誰でも合格ラインに届く!
社労士になるためには、年に一度実施される国家試験「社会保険労務士試験」に合格する必要があります。この試験は屈指の難関として知られており、合格には相応の覚悟と戦略的な学習が不可欠です。
試験の難易度と合格率のリアル
社労士試験の合格率は例年6〜7%前後で推移しており、非常に低い水準です。他の国家資格と比較しても、その難易度の高さがわかります。
| 資格名 | 近年の合格率(目安) |
|---|---|
| 社会保険労務士 | 6~7% |
| 宅地建物取引士 | 15~17% |
| 行政書士 | 10~15% |
| 中小企業診断士(最終) | 4~8% |
| 司法書士 | 4~5% |
なぜこれほど難しいのか。その理由は、試験範囲が非常に広範であること、そして各科目に「足切り」となる合格基準点が設けられていることにあります。全10科目に及ぶ法律を網羅的に学習し、かつ、どの科目も最低ラインをクリアしなければならないため、苦手科目を一つでも作ることが許されません。
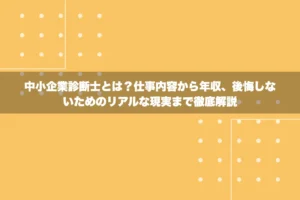
合格に必要な勉強時間と独学の可能性
合格に必要な勉強時間は、一般的に800〜1,000時間と言われています。働きながら1年での合格を目指す場合、平日2時間、休日5時間といった学習をコンスタントに続ける計算になります。
独学での合格も不可能ではありません。しかし、広範な試験範囲と頻繁な法改正に対応し、モチベーションを維持し続けるのは至難の業です。
多くの場合、予備校や通信講座を活用する方が効率的かつ確実と言えるでしょう。最新の法改正情報や試験の傾向分析、質の高い教材を利用することで、合格の可能性を大きく高めることができます。
効果的な勉強法3つのポイント
難関試験を突破するためには、がむしゃらに勉強するだけでは不十分です。以下の3つのポイントを意識して、戦略的に学習を進めましょう。
1. 過去問を制する者は試験を制す
過去問は、出題傾向や問われる知識のレベルを知るための最高の教材です。最低でも過去5〜10年分を繰り返し解き、すべての選択肢について「なぜ正しいのか」「なぜ誤っているのか」を説明できるレベルを目指しましょう。これにより、知識が定着し、応用力が身につきます。
2. 理解重視の学習を心がける
膨大な暗記事項に圧倒されがちですが、単なる丸暗記には限界があります。「なぜこの法律(制度)があるのか?」という背景や趣旨を理解することで、知識が有機的に結びつき、忘れにくくなります。特に、複数の科目にまたがる横断的な学習は、理解を深める上で非常に有効です。
3. スキマ時間を徹底的に活用する
まとまった勉強時間を確保するのが難しい社会人にとって、スキマ時間の活用は合否を分ける重要な要素です。通勤中の電車内、昼休み、寝る前の15分など、細切れの時間をスマートフォンアプリや音声教材で活用する習慣をつけましょう。この小さな積み重ねが、大きな差となって現れます。
 キャリまる
キャリまる「続けられる環境作り」が合格の近道。生活リズムに勉強を組み込もう!
- 合格率6〜7%。全10科目+足切り制度が難しさの理由
- 学習時間800〜1,000時間。1日2〜3時間を1年間が目安
- 独学も可能だが、通信講座の併用が合格率を押し上げる
「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室⑦
「試験ってそんなに難しいんですか…?」
 優菜さん
優菜さんところでキャリまるさん…社労士試験って、やっぱり超ムズイんですよね…?
 キャリまる
キャリまるうん、正直、簡単ではない! 合格率は6〜7%前後。でも、ちゃんと対策すれば到達できるよ。
 優菜さん
優菜さんバイトしながらでも受かりますか?
 キャリまる
キャリまるもちろん!働きながら1年で合格する人もたくさんいる。コツはこの3つかな。
✅ 過去問を“解く”だけじゃなく“分析”する
✅ 丸暗記じゃなく、背景から“理解”する
✅ スキマ時間を徹底的に活用する(スマホ教材とか活用)
 優菜さん
優菜さんやみくもにやるんじゃなくて、“戦略的に勉強”が大事なんですね…!
社会保険労務士のQ&A
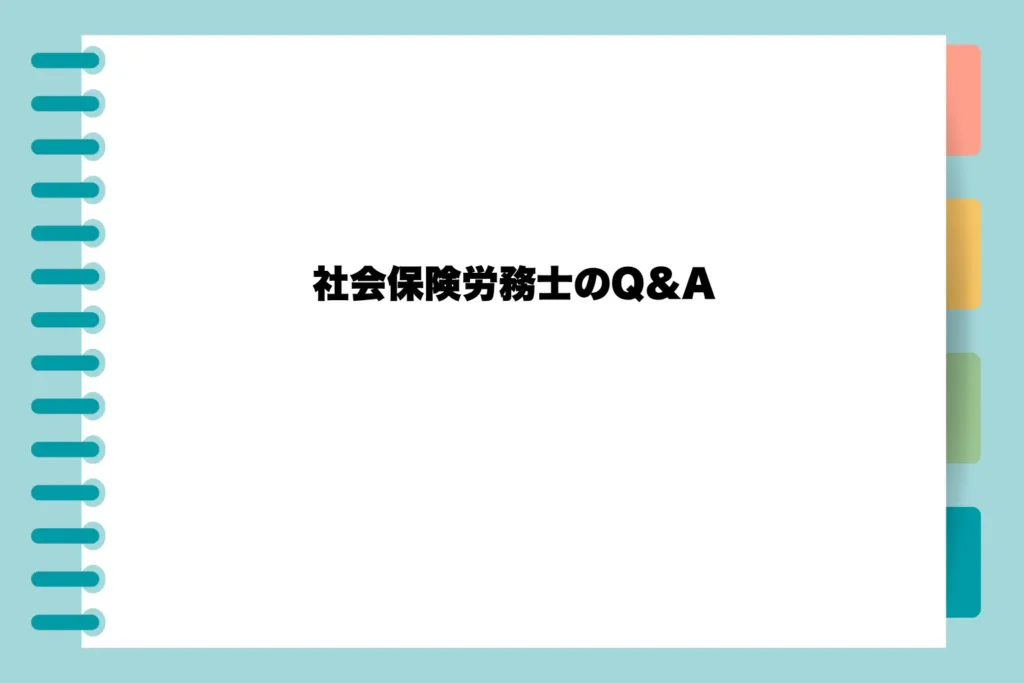
社労士は何をする職業ですか?
社労士(社会保険労務士)は、会社の「人」に関する手続きやルール作りの専門家です。もっとわかりやすく言うと、「会社と働く人の間にある“面倒で複雑なこと”をスムーズにする仕事」です。会社の“人”に関わる悩みや手続きを、法律と実務の知識でサポートする専門職。会社にとっても、働く人にとっても、とても大事な存在です。
社労士は何をしてくれるの?
社労士(社会保険労務士)は、企業にとって面倒で複雑な「人」に関することを、専門知識でサポートしてくれるプロフェッショナルです。
まず、社員の入退社にともなう社会保険や雇用保険の手続き。
会社が役所に提出しなければならない書類を、代わりに作って提出してくれます。これは地味ですが、実は会社にとってかなり大きな負担なので、外注するととても助かります。
次に、就業規則の作成や見直しのアドバイス。
「残業代はどう決めればいい?」「パワハラ防止のルールは?」といった、会社のルール作りを法的にサポートしてくれます。これがあると、後のトラブルを防げます。
さらに、労務トラブルへの相談対応もしてくれます。
「社員が無断欠勤を続けている」「退職後に残業代を請求された」など、会社と社員の間に起こる問題に対して、どう動けばいいかをアドバイスしてくれます。
また、助成金の申請サポートもよく依頼されます。
国の制度をうまく使って「人を雇ったらもらえるお金」を申請する際、書類作成や条件チェックをしてくれるので、損を防ぐことができます。
社労士の年収はいくらですか?
たとえば、会社員として企業の人事部や社労士事務所で働いている人(いわゆる「勤務社労士」)の場合、年収はだいたい400万円〜600万円前後が一般的です。大企業の人事部や管理職になると、700万円以上もありえますが、平均的にはこのくらいが相場です。
一方で、開業して自分で事務所を持つ「独立社労士」になると、年収はピンキリです。
軌道に乗るまでは年収200〜300万円台のこともありますが、実績を積んで法人顧客を多数抱えたり、助成金申請や顧問契約が増えてくると、年収1,000万円を超える人も珍しくありません。
社労士になるのは何ヶ月で取れる?
社労士になるまでに必要な勉強期間は、一般的には6ヶ月〜1年半ほどです。これはあなたの状況や使える時間によって大きく変わります。たとえば、毎日2〜3時間しっかり勉強できる人なら、半年〜9ヶ月ほどで合格を目指すことも可能です。これは通信講座や予備校の短期合格カリキュラムでもよく見られるペースです。
一方で、仕事や家事をしながらスキマ時間で勉強する人は、1年〜1年半くらいかけてじっくり合格を目指すのが一般的です。週10時間ほどの学習ペースならこのくらいかかると考えておくと安心です。
勉強時間の目安としては、トータルで800〜1,000時間程度が合格ラインとよく言われます。
社労士の資格は難しいですか?
はい、社労士の資格はかなり難しい部類に入る国家資格です。まず、試験範囲が広いのが特徴です。労働基準法や労災保険、雇用保険、厚生年金、国民年金、労働保険徴収法、労働一般常識など、まさに「働く人」と「会社」を取り巻く法律のオンパレード。しかも、それぞれの法律が頻繁に改正されるため、最新の知識が求められます。
次に、合格率が低いことも難しさの理由の一つ。社労士試験の合格率は、毎年だいたい5〜8%前後。つまり、受験者のうち10人に1人も受からないこともあるという厳しい試験です。
さらに、1点のミスで不合格になることもあるほど、試験制度がシビアです。科目ごとの足切り点(基準点)があり、どれだけ全体の点数が良くても、1科目でも基準を下回ると落ちてしまいます。
社労士資格は就活に有利ですか?
社労士資格は、就活で一定のアピール材料にはなりますが、強く有利になるかは「志望業界・職種次第」です。人事・労務・総務系の職種を志望する場合は、社労士資格があることで「基礎知識がある」「入社後すぐに戦力になりそう」と評価されやすく、かなり好印象です。特に中小企業や人事を重視する企業では高く評価されることがあります。
また、社労士事務所や社会保険関連のアウトソーシング会社を受ける場合は、資格そのものが業務に直結するため、ほぼ必須または優遇されることが多いです。
社労士はどこで就職できますか?
社労士は、「人事・労務の専門家」として、さまざまな場所で活躍できます。代表的なのは、社労士事務所や労務コンサル会社。
ここでは企業の代わりに社会保険手続きや給与計算、就業規則の作成などを行い、複数のクライアント企業を担当します。実務経験を積みたい人にはピッタリの環境です。
次に多いのが、一般企業の人事・総務部門です。
社労士の資格を持っていると、採用・労務管理・勤怠・福利厚生などの仕事で知識が活かせます。中小企業では「人事の即戦力」として歓迎されることもあります。
また、社会保険労務士法人や大手会計事務所のグループ企業にも就職できます。
これらの法人では、労務コンサルや助成金申請サポートなど、高度なサービスを提供しているため、専門性を活かしたキャリアを築けます。
さらに、公的機関や独立行政法人でも活躍の場があります。
労働局、ハローワーク、年金事務所、商工会議所、自治体の中小企業支援センターなどで、企業や労働者の相談対応を行うケースもあります。
「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室⑧
「社労士って、就活生が目指す資格として“アリ”ですか?」
 優菜さん
優菜さんじゃあ先輩、結局のところ…就活生が社労士を目指すのって“アリ”ですか?
 キャリまる
キャリまるズバリ言うと、“専門性を持ってキャリアを自分で切り拓きたい人”には、めちゃくちゃアリ。
法律や人事に興味がある
長期的に資格を活かして働きたい
将来自分で働き方を選べるようになりたい
 キャリまる
キャリまるこういう思いがある人には、社労士は“一生モノの武器”になると思うよ。就活前に勉強始めても、面接やESで“視点の違い”が出せるし。
 優菜さん
優菜さんちょっと本気で考えてみたくなりました…!
まとめ:社労士は「人」を支える、将来性ある専門職
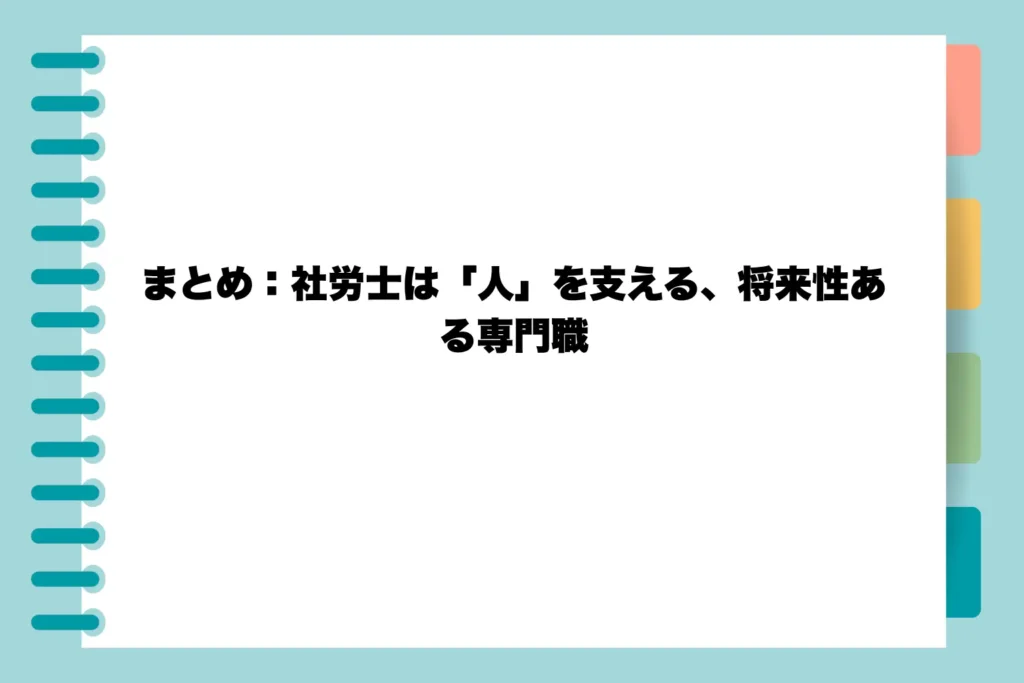
本記事では、社会保険労務士の仕事内容から年収、働き方、将来性、そして試験の難易度まで、現役社労士の視点からリアルな情報をお届けしました。
社労士は、「人」に関する専門家として、企業の成長と従業員の働きがいを支える、社会的に非常に意義のある仕事です。試験は難関で、独立開業の道は決して楽ではありません。しかし、AI時代においてもその専門性は揺るがず、むしろ複雑化する社会においてその価値はますます高まっています。
もしあなたが「会社に依存しない専門性を身につけたい」「法律の知識で人の役に立ちたい」と強く願うなら、社労士は挑戦する価値のある魅力的なキャリアです。この記事が、あなたのキャリア選択における確かな一歩となることを心から願っています。まずは公式サイトで試験概要を確認したり、予備校の無料セミナーに参加したりして、次のアクションを起こしてみてはいかがでしょうか。
参考サイト
- https://www.shakaihokenroumushi.jp/
- https://www.shakaihokenroumushi.jp/
- https://japan-adr.or.jp/search/adr_agency_2120870615.html
- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8A%B4%E5%8B%99%E5%A3%AB